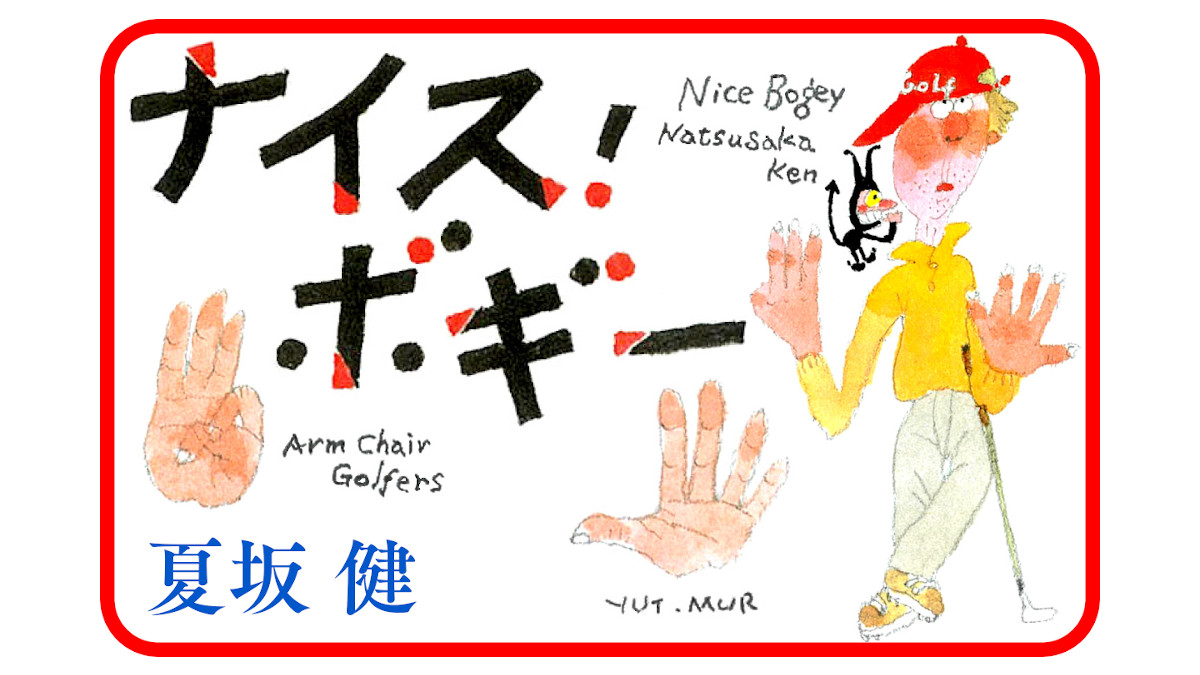あのパーマー、バロステロスも緊張してアガっていた 「ジ・オープンに参加した選手は、他のメジャーと異なるプレッシャーに遭遇して、落ち着かないこと夥しいのが普通なのさ。だってトロフィーに刻まれた歴代チャンピオンの名前を見てご…
画像ギャラリー今から20数年前、ゴルフファンどころか、まったくゴルフをプレーしない人々までも夢中にさせたエッセイがあった。著者の名は、夏坂健。「自分で打つゴルフ、テレビなどで見るゴルフ、この二つだけではバランスの悪いゴルファーになる。もう一つ大事なのは“読むゴルフ”なのだ」という言葉を残した夏坂さん。その彼が円熟期を迎えた頃に著した珠玉のエッセイ『ナイス・ボギー』を復刻版としてお届けします。
夏坂健の読むゴルフ その40 コメントで綴る「全英オープン」
1ヵ月前に泳いで出発しても参加したい
「コーネル・マンディという名のプロを知ってるかね? 彼は世界各地で開催されるマイナー競技の情報に精通した男だ。ポルトガル、フィンランド、ウガンダ、シンガポールから南米のコロンビアまで神出鬼没、賞金は大したことなくても出場回数が凄い。恐らく何百万ポンドも稼いでいるだろう。だが、ゴルフではメジャーで一勝しない限り、その選手のキャリアは完璧とは言えない。メジャーの勝者だけが『トップ』であって、あとはどう弁護しようとも二流、三流なのだ。コーネル・マンディには申し訳ないが、たとえ地方で100勝しようとも彼はただの平凡なプロにすぎない」(評論家、ラス・ヘンドリックス)
「全米オープンのチャンピオンは怒るかも知れないが、同じメジャーでも全英オープンには比類なき重みがある。学校の運動会とオリンピックの違い、なんて言うつもりはないが、まあ、いくらアメリカでも歴史だけはカネで買えないからね」(『ジ・オープン』の編者、ダン・サイクス。説明するまでもなく彼はイギリス人だ)
「1860年の第1回大会以来、ジ・オープンの勝者には『人生の特別な椅子』が用意される。優勝したその日から、たとえばフライド・ポテトの店に入ってさえ、
『あの人が、ジ・オープンのチャンピオンだよ』
と、尊敬の念で迎えられ、人々から特別視される快適さは終生変わることがない。このあたりが他のメジャーと大いに異なる点だ。誰がなんと言おうと勝つならジ・オープンに限ると思うね」(ピーター・トムソン。全英に5勝したが、スモールボールの使用禁止で威勢が悪くなった代表的な1人)
「あれがゴルフコースだって!? アメリカならトラック置き場にしかならないシロモノだね」(サム・スニード。1946年当時、車窓から初めてセントアンドリュースを見たときの発言)
「ストローハットの男(スニード)が聖地を冒瀆した。猟銃で撃ち殺してもいいが、それでは一種の安楽死にすぎない。そこでわれわれキャディ一同は、彼のバッグ担ぎを拒否することで意見が一致した。あの男はセルフでプレーすることになるだろう」(キャディの声明文より)
「倍の料金で経験者を雇ったが、ヘンなのばかりだ。優勝したときのキャディは目に一杯の涙をためて、
『家宝にしますから、どうぞウィニングボールをください』
と、くどく懇願したものだ。ところがボールを渡した直後、1人の好事家に50ポンドで売っ払ったのだから、開いた口が塞がらないね」(サム・スニード)
「歴代チャンピオンとして、貴殿には出場する義務がある」(競技委員会からスニードへの書状)
「優勝したところで、貰えるのはアメリカ貨幣でわずか600ドルだ。あの金額で大西洋を行ったり来たりするとなると、俺は200歳まで球打ちに励む必要に迫られる。いっぺん勝ったのだから、もう俺には構わないでくれよ」(サム・スニード)
「自分としては、カネより名誉が大事だと思う。もし乗り物が全部ストライキ中だというなら、1ヵ月前に泳いで出発しても参加したいトーナメントだね」(リー・トレビノ)
あのパーマー、バロステロスも緊張してアガっていた
「ジ・オープンに参加した選手は、他のメジャーと異なるプレッシャーに遭遇して、落ち着かないこと夥しいのが普通なのさ。だってトロフィーに刻まれた歴代チャンピオンの名前を見てごらんよ。トム・モリス、ハリー・バードン、ヘンリー・コットン、ボビー・ジョーンズといった伝説の巨人たちがキラ星のように並んでいるんだ。次の瞬間、自分がとても小さく感じられて、どうふる舞っていいのかわからなくなる。かなりのベテランでも、初日のスタート前には10回ほど空ツバを飲み、10回ほど深呼吸してからティアップするほどアガっている。あのパーマーでさえ初参加の1番、ティペッグがあるつもりでボールをじかに置いたもの」(1960年度のチャンピオン、ケル・ネーグル)
「もし100歳まで生きて、1つだけ思い出のゲームが脳裏に残るとしたら、それはジ・オープンの第100回記念大会だろうね。1960年、セントアンドリュースの夏、私は怖いもの知らずの若者だった。もちろん、4日間のショットの全部を覚えている。スコアは『70・71・70・68』だったが、この中にはラフで合計5回も手こずった分も入っている。凄いだろ?」(アーノルド・パーマー)
「世界を手に入れた瞬間が味わいたかったら、ジ・オープンで優勝するしかない。シーザーもアレキサンダーも、チャンピオン以上に欣喜雀躍したことがあるだろうか」(ジャック・ニクラウス)
「まず風が吹く。いつかやむと思うのだが、どこにエネルギー源があるのか一向にやまない。風の中のプレーは5倍も疲れる。加えてラフのすさまじいこと、夜にはフォークも満足に握れない。見る夢といったら背丈の隠れるほどの茂みで苦闘する姿ばかり。4日目には4キロも瘦せて、スパイクを履くのさえ大儀になる。ジ・オープンというのは本当につらいゲームの連続だ。気がついたかね? 1世紀以上も続くトーナメントだというのに、かつて選手も役員も笑ったことがない。いつの試合であれ、ジ・オープンには笑顔と女の役員は存在しないのだ」(へール・アーウィン)
「1979年のロイヤル・リザム・アンド・セントアンズでは、ティショットが満足に打てないほど緊張していた。真ん中に飛んだのは数発だけ、あとはラフ伝いの毎日だった。ところがゴルフは皮肉、かつてないほどアプローチが冴えてパットも入る。優勝したとき、作家のダン・ジェンキンスが僕に言ったものだ。
『あれ!? きみは観客整理係かと思ったよ』」(セベ・バレステロス)
「ジ・オープンに賞金が出たのは第4回大会から。1876年の勝者ボブ・マーチンが得たのは、たったの10ポンドにすぎない。1899年の勝者ハリー・バードンが50ポンド、1920年に13打の大差をひっくり返して優勝したジョージ・ダンカンが、ようやく100ポンドを得ている。いまと貨幣価値が異なるといっても、そう大した金額ではない。要するにジ・オープンでは名誉が最大の関心事だったことを、歴史が如実に証明している。ところが昨今では途方もない賞金だ(注・邦貨約4000万円以上)。カネが名誉を上回ったとき、伝統の精神に亀裂が入ること必定。21世紀のジ・オープンは、野趣が売り物のトリックショットのショーになるかも知れない」(評論家、トーマス・ポッターハウス)
「なんでもいい。とにかく僕はジ・オープンで優勝したかった。子供のころ、
『これが入れば優勝だ!』
感動のシーンを夢想しながらパッティングに耽ったものだった。それが現実となって、いま、どうしていいかわからない」(ニック・ファルド。1987年のミュアフィールドで初メジャーを制したとき)
「ジ・オープンで優勝してからの1ヵ月間、毎日6時間も祝賀電話の相手をしていた。メジャーの中でも、あの試合は特別なのさ」(イアン・べーカーフィンチ。1991年のチャンピオン)
(本文は、2000年5月15日刊『ナイス・ボギー』講談社文庫からの抜粋です)
夏坂健
1936年、横浜市生まれ。2000年1月19日逝去。共同通信記者、月刊ペン編集長を経て、作家活動に入る。食、ゴルフのエッセイ、ノンフィクション、翻訳に多くの名著を残した。毎年フランスで開催される「ゴルフ・サミット」に唯一アジアから招聘された。また、トップ・アマチュア・ゴルファーとしても活躍した。著書に、『ゴルファーを笑え!』『地球ゴルフ倶楽部』『ゴルフを以って人を観ん』『ゴルフの神様』『ゴルフの処方箋』『美食・大食家びっくり事典』など多数。