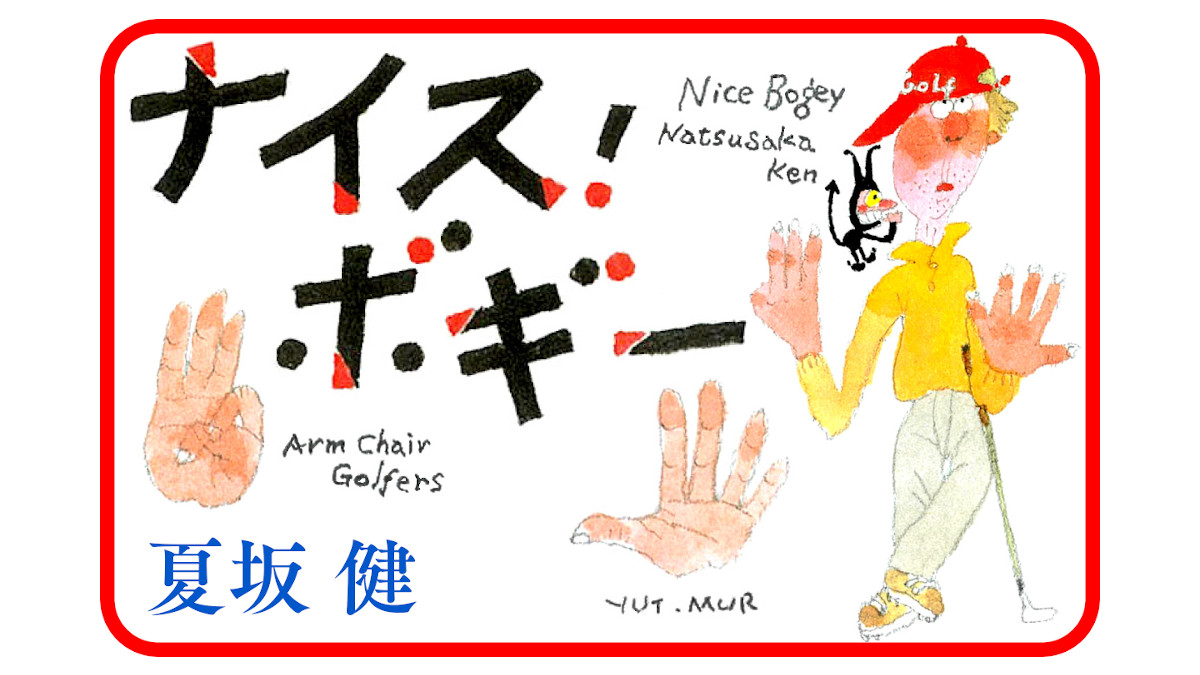ゴルフとは本来残酷と威厳が同居するゲームだから 1972年のペブルビーチでは、温厚なジョージ・アーチャーが珍しく怒った。 「全米オープンとは、選手一同を逆上させて、誰が一番冷静だったかを調べるUSGA主催のテスト会場だ」…
画像ギャラリー今から20数年前、ゴルフファンどころか、まったくゴルフをプレーしない人々までも夢中にさせたエッセイがあった。著者の名は、夏坂健。「自分で打つゴルフ、テレビなどで見るゴルフ、この二つだけではバランスの悪いゴルファーになる。もう一つ大事なのは“読むゴルフ”なのだ」という言葉を残した夏坂さん。その彼が円熟期を迎えた頃に著した珠玉のエッセイ『ナイス・ボギー』を復刻版としてお届けします。
夏坂健の読むゴルフ その43「全米オープン」の深いラフ
USGAは、心の歪んだ老婆の集団である
それが天下分け目のスーパーボウルだからといって、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)が、競技場の長さを200ヤードも伸ばしたことがあるだろうか。
NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)にしても、プレーオフに備えてゴールポストを10ヤードほど高くしたりはしない。
「ところが唯一、USGA(全米ゴルフ協会)だけが暴君ネロも顔負け、傲慢な態度を崩そうとしない。協会に巣食っている石頭の一味は、ナショナル大会でアンダーパーが記録されるのは国家的屈辱だと考えている。そこでラフを1年間も伸ばし放題にすると、次にアイススケートが出来るほどピカピカにグリーンを刈り込み、最後にスーパーマーケットの通路より狭いフェアウェイに仕立ててご満悦だ。USGAは、ナチス親衛隊より加虐的な存在であり、選手いじめの天才によって構成された世界で最も隠微な集団である」
これまで、実に多くの選手と関係者が全米オープンのコース設定について非難してきたが、ここに紹介したコラムニスト、ティム・ロサフォーツの場合、毎年6月のゲーム終了と同時に吠え立てるので、いまや彼のクレームも季節の風物詩と化した感がある。
ティムの研究によると、第二次大戦前まで全米オープンは至ってフェアに運営されてきた。ところが1946年、オハイオ州のカンタベリーGCで試合が再開された際、長く続いた戦争によってコースが荒れ果て、ロイド・マングラムとプレーオフにもつれ込んだ復員軍人ビッグ・ゲッツは、生い茂る猛烈なラフに負けて手首を捻挫、ホールアウトするのがやっとだった。
「この苛酷なゲームから、USGAの連中は天の啓示を受けたに違いない。即ち、コースの難易度が高いほどスリルとサスペンスのヴォリュームも高くなるという真理の発見だ」
それでもティムは傍観者の一人にすぎない。たまらないのは選手たち、翌年のセントルイスCC大会から現在まで、ブーイングは年ごとに大きくなるばかり。
「あまりにもフェアウェイが狭いので、俺たち選手は一列になって歩くしかない状態だった」
オークランドヒルズで行われた1951年の大会で、ケリー・ミドルコフがマイクに向かって叫ぶと、優勝したべン・ホーガンまでが珍しく愚痴ったものである。
「もし毎週、このコースでプレーしろと言われたら、俺はゴルフから足を洗って別な仕事を探すね」
選手たちの悲鳴もUSGAにはマゾの嬌声に聞こえるらしく、コース設定はさらに過酷さを増していった。オリンピックC、オークモントCC、バルタスロールGCと、回を重ねるたびに「選手いじめ」の様相は濃くなる一方。1970年のへーゼルタインGCでは、ついに恐れていたハプニングが発生した。
その週の火曜日、練習のためコースにやってきたデイブ・ヒルは、4ホール回っただけで家に帰ってしまった。膝が隠れるほど伸びたラフ、セメントで固めたかといぶかる高速グリーン、最大幅でも25ヤードしかない路地のようなフェアウェイ。
「私は瘦せて小柄だ。腕力が要求されるコースでは予選通過も無理だろう」
そして、次のように言った。
「USGAは、心の歪んだ老婆の集団である。彼らは自分たちこそゴルフにおける貴族の後継者だと自負し、年に一度全米オープンがめぐってくると、昔のアマ気質をプロに見せつけるためしゃしゃり出てくる。選手の悲鳴が大きいほど、彼らは屈服させた快感に酔い痴れる異常者だ」
彼に同調して、3人のプロが帰ってしまった。ボブ・ロスバーグの言葉を借りると、へーゼルタインGCとは、
「80エーカーのトウモロコシ畑と、数頭の牛がいるだけの原野」
であり、どこもかしこも深いラフに覆われて、フェアウェイから1ヤード外れた瞬間、1ペナルティが科せられたのと同じ結果になる。ボブの場合、4日間プレーしたが、最終日には腕が疲れて満足にグリップもできない状態だった。丸太のような腕の持主が、そう言うのである。
ゴルフとは本来残酷と威厳が同居するゲームだから
1972年のペブルビーチでは、温厚なジョージ・アーチャーが珍しく怒った。
「全米オープンとは、選手一同を逆上させて、誰が一番冷静だったかを調べるUSGA主催のテスト会場だ」
言い捨てるなり、彼は6個ものボールを意図的に太平洋めがけて打ち放った。1982年、再びペブルビーチで開催されたとき、記者団の質問にコース管理責任者はこう答えたものだ。
「USGAの申し付けに従って、グリーンをフライパンの底みたいに刈り込み、ラフは伸ばし放題のまま、もう半年も知らん顔です。役員のうち、2人ぐらいしか80を切れないと判明して、準備OKというわけです」
選手側からの非難も、いまではヤケ気味である。
「もし、すべてのグリーンのド真ん中に池を作ることが可能ならば、USGAはそうするだろう」(デイブ・ストックトン)
「渡り廊下のようなフェアウェイなんぞ残さないで、いっそ全面ラフにしたらどうだい? その上でルールに若干手直しを加えて、ヒゲが剃れるぐらいアイアンのブレードを研ぐのさ。そうなると農夫出身のピーター・ジェイコブソンとジム・コルバートが、交互に優勝するだろうね」(チチ・ロドリゲス)
「幾重にも渦巻いた草の下に、ちょっぴりボールがのぞけていた。ヨチヨチ歩きのころからクラブを握っているが、こんな状態でのショットは練習したこともない。そこで横にいたUSGAのオフィシャルに、精一杯の皮肉を込めて尋ねてみた。
『アメリカでは、地中深く潜ったボールをどうやって打つのかね?』
すると彼は、口の端を歪めて意地悪そうにこう言ったものさ。
『アイアンで……』
プッツンした私は、空振りこそしなかったものの、10センチ前進しただけでゲームから見放された」(セベ・バレステロス)
「誰が勝つか予想しろって? それは丸1年間、真剣にグリップ強化器と取り組んだ奴に決まってるじゃないか」(ヘール・アーウィン)
「全米オープンでは、USGAが対戦相手となる。日ごろのライバルたちも、この試合に限って羊の家族の兄弟だ」(アーノルド・パーマー)
いかに泣こうが喚こうが、USGAの耳には届かない。オフィシャルの一人、フランク・ハニンガムは次のように宣うた。
「全米オープンでは、すべてのドライバーが冒険であり、すべてのアイアンショットが不安と緊張のピークで打たれる。そしてパッティング、これこそがスペクタクルであるべきだ。選手の神経がいかに金属音を発しようとも、それは当方と無関係、ゴルフとは本来残酷と威厳が同居するゲームだからである」
1996年の全米オープンは、「モンスター」の異名があるオークランドヒルズで開催される。現地からの報告によると、ラフの発育は上々らしい。
(本文は、2000年5月15日刊『ナイス・ボギー』講談社文庫からの抜粋です)
夏坂健
1936年、横浜市生まれ。2000年1月19日逝去。共同通信記者、月刊ペン編集長を経て、作家活動に入る。食、ゴルフのエッセイ、ノンフィクション、翻訳に多くの名著を残した。毎年フランスで開催される「ゴルフ・サミット」に唯一アジアから招聘された。また、トップ・アマチュア・ゴルファーとしても活躍した。著書に、『ゴルファーを笑え!』『地球ゴルフ倶楽部』『ゴルフを以って人を観ん』『ゴルフの神様』『ゴルフの処方箋』『美食・大食家びっくり事典』など多数。