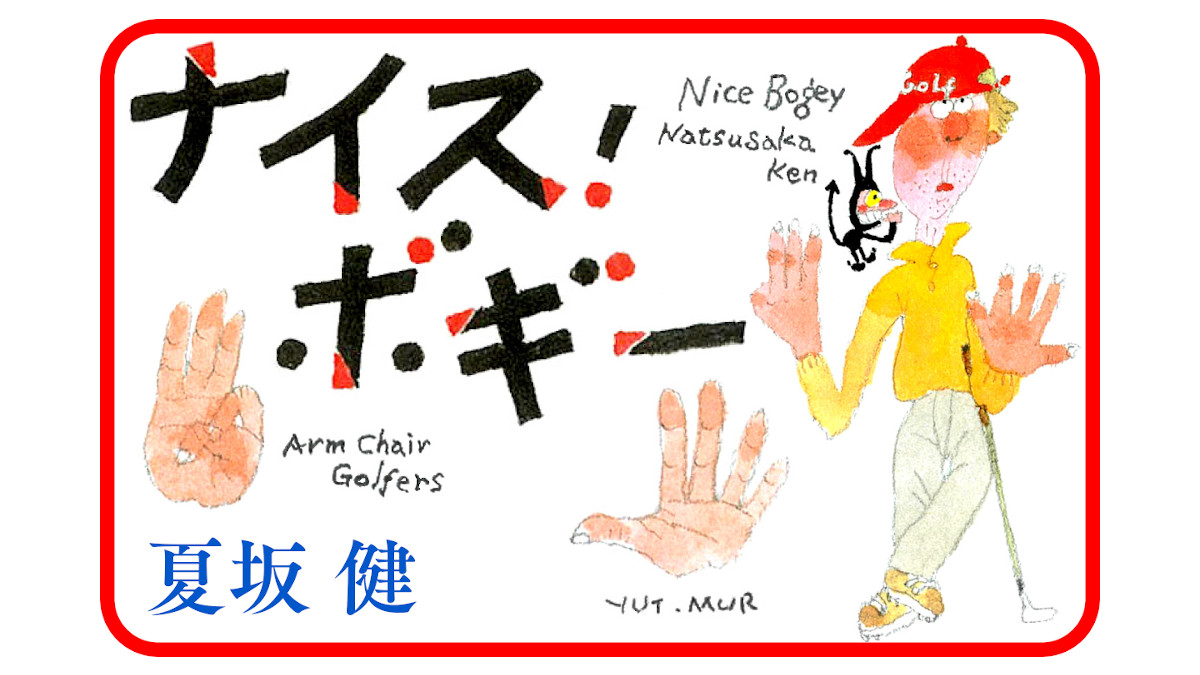夏坂健の読むゴルフ「ナイス・ボギー」その13 詩人の愉しみ 今から20数年前、ゴルフファンどころか、まったくゴルフをプレーしない人々までも夢中にさせたエッセイがあった。著者の名は、夏坂健。「自分で打つゴルフ、テレビなどで…
画像ギャラリー夏坂健の読むゴルフ「ナイス・ボギー」その13 詩人の愉しみ
今から20数年前、ゴルフファンどころか、まったくゴルフをプレーしない人々までも夢中にさせたエッセイがあった。著者の名は、夏坂健。「自分で打つゴルフ、テレビなどで見るゴルフ、この二つだけではバランスの悪いゴルファーになる。もう一つ大事なのは“読むゴルフ”なのだ」という言葉を残した夏坂さん。その彼が円熟期を迎えた頃に著した珠玉のエッセイ『ナイス・ボギー』を復刻版としてお届けします。第13回は、ゴルフに関する至高の名言を残した詩人について。
読書とゴルフにハマった天才少年
酔いがまわるにつれて、スコットランドの男衆はようやく重い唇を動かすと、誰もが聞き取りにくい発音で似たような身の上話をする。
「俺が生まれたのはコースの近くだ。ハイハイを覚えたのもバンカーの中。ラフで隠れん坊しながら大きくなると、グリーンを横切って学校に通ったものよ」
要するに、コース生まれのコース育ち、自分はゴルフの申し子だと言いたいのである。確かに、彼らにとってゴルフは呼吸するのと同じくらい自然であり、空気と同様の存在であることだけは間違いない。
さて1844年、スコットランドに生まれたアンドルー・ラングも、視野の片隅に四六時中ピンフラッグがはためく環境の中で成長した。幼いころから腺病質だったこともあって、近在にあるすべての書物を読み漁り、稀なる天才少年と呼ばれた。ところが10歳ごろからゴルフに嵌まって抜き差しならない事態。読書か、プレーか、彼の人生はこの両輪によって回転し始めた。
オックスフォード大学で学問を修めたあと、再び故郷に戻って民間伝承の研究に取り組んだ彼は、スコットランドからシェットランド諸島までくまなく歩き、古老たちに昔話を聞き、古文書と格闘する日々を送った。人名辞典によると、彼の肩書は「歴史家、古典学者、民俗学者、詩人、大学教授」となっているが、この際の取材紀行が偉大なる史家誕生のきっかけとなった。論壇へのデビューは、土俗伝説が文学的神話の基礎になることを証明した『Custom and myth』(1884年)だった。やがてスチュアート王家の歴史に興味を持った彼は、『History of Scotland』全4巻と『The mystery of Mary Stuart』を発表して、揺るぎない地位を築いた。
こうした仕事とは別に、不滅のギリシャ神話や叙事詩「オデュッセイア」「イーリアス」などを英訳、別に何冊かの童話まで出版しているのだから、その創作意欲たるや絶倫、スコットランド人がいまだに国民的英雄として扱うのも当然すぎる話である。
もちろん、年齢と共にゴルフ熱も高まる一方。27歳ごろになると、愛するゲームの素顔をさまざまな角度から詩によって賛美するようになった。たとえば、これからスタートするゴルファーの心境を次のように歌い上げる。
「ひめやかに咲く黄の花の微香
冷麗たるスコットランドの草原に満つ
幾星霜の聖地に向け
まさに優遊のとき来たれり
いざ友よ、哲学の散策に赴かん
彼方に待ち受ける悽愴の試練か
はたまた快心の哄笑か
願わくは神よ、われにひと握りの幸運を!」
あるいは、ゲームに要求される不退転の決意と、ゴルファーであることの誇りについて朗々と歌うのだ。
「暗雲幽々、風雨咆哮せり
たとえ前途に幾千万の苦難があろうとも 騎士たる者、断じて臆するべからず
篠つく雨、さらに激しく、コースを行き交う者 みな老いたる魚の如し
これまた欣快なり
われ、ゴルフをせんと生まれけむ」
この最後のくだりが、身震いするほど素晴らしい。天候に文句ばかりつける近ごろの脆弱な奴らに、額装して送り付けたい言葉である。
自身のドライバーに対する思いを綴った傑作
セントアンドリュースをこよなく愛した彼に、ある日一通の手紙が舞い込む。これぞ待ちに待った吉報、積年の念願叶ってセントアンドリュース大学の教授に迎えられたのだ。と同時に、伝統あるクラブの会員として入会も許されたのだから、二重の喜びだった。クラブ史によると、正式入会が許されるのが1月1日。ところが古いしきたりが黙殺されて、前年の9月15日から会員として迎えられている。この一事を以てしても彼がいかに愛された存在か、よくわかるというものだ。セントアンドリュースの名物プロ、アンドリュー・カーカルディーが残した日記に、しばしば彼が登場する。
「ラング教授は、どちらかというと細い体のお人だった。飛距離に悩んでいなさったが、ゴルフは小技のゲームと承知、アプローチとパッティングでしぶといゴルフを身上とされた」
日記には、思いがけない素顔も登場する。セントアンドリュースの名物キャディ、「オールド・ドゥ」といえば、かつてアラン・ロバートソン、ウィリー・パークなど、巨星たちのキャディをつとめたことでも知られるが、長男のジェミー・アンダーソンが1877年から全英オープンに3連勝したこともあって、周囲から隠居を迫られ、ひところはマッセルバラに引っ込んでいた。しかし、愛しのセントアンドリュースが忘れられず、理事会に頼んで9番ホールの横にジンジャービールとレモンスカッシュの売店を構えることになった。
誰よりも、この地をこよなく愛したアンドルー・ラングにすると、「オールド・ドゥ」が親戚のように思えてならなかった。日記によると、彼は9番に到着するのが待ち切れない様子、プレーもそこそこに屋台まで出向くと、握手の手も離さずに体の具合を尋ね、それからジンジャービールを求めて、必ず同じ質問をするのだった。
「売れてるかね?」
すると、正直者のドゥも判で押したように同じ答えを繰り返した。
「どのくらい売れてるか、家に帰って帳簿を見ないとわかりません」
「儲かっていれば、それで十分だ」
「原価についても、帳簿を見ないとわかりません」
するとラングは大笑いしたあと、決まって同伴者に言うのだった。
「ドゥは、スコットランド随一の正直者だね」
9番に限らず、彼はコースで行き交う人に近づいては挨拶を交わし、管理人と話し込み、この地に対する愛情が全身から溢れていた。ところがゴルフだけはままならず、セントアンドリュース大学の学内誌「カレッジ・エコー」に、自分のドライバーに対する悪態を次のように綴ったことがある。
「ドライバーよ!
お前は痛風病みのロバ 後家のキツネ 頭痛持ちのフクロウ 臆病者のヘビ 高慢ちきな令嬢 二日酔いの運転手
これでも、まだまだ言い足りぬ
お前は目隠しされたヒバリ 羽根を落としたトンビ 手紙を失くした郵便屋 陽気がいいのに咲かぬ花 引き金の壊れたピストルだ
お願い、たのむ せめて一度でいい、自分の役目を思い出しておくれ」
八つ当たりの詩かと思えば、なんのことはない、最後は哀願である。それにしても、ここまで悪態をつかれたドライバーが期待に応えるとは思えない。カーカルディーの証言を待つまでもなく、彼がティショットに問題を抱えていたことは明白である。
1912年7月20日、彼は膨大な著作と、同じく膨大なスコアカードの山を残してこの世を去るが、常に身辺に置かれた備忘録の最後のページに、若いころ書いた詩の一節が几帳面な書体で小さく綴られてあった。生涯に数千の詩を残したが、恐らくこの一文こそ自ら傑作の折り紙をつけたものに違いない。
『われ、ゴルフをせんと生まれけむ』
(本文は、2000年5月15日刊『ナイス・ボギー』講談社文庫からの抜粋です)
夏坂健
1936年、横浜市生まれ。2000年1月19日逝去。共同通信記者、月刊ペン編集長を経て、作家活動に入る。食、ゴルフのエッセイ、ノンフィクション、翻訳に多くの名著を残した。毎年フランスで開催される「ゴルフ・サミット」に唯一アジアから招聘された。また、トップ・アマチュア・ゴルファーとしても活躍した。著書に、『ゴルファーを笑え!』『地球ゴルフ倶楽部』『ゴルフを以って人を観ん』『ゴルフの神様』『ゴルフの処方箋』『美食・大食家びっくり事典』など多数。
画像ギャラリー