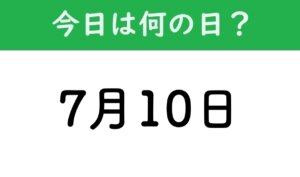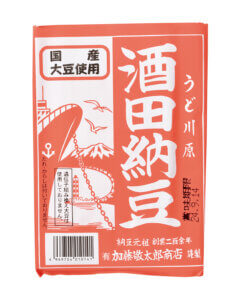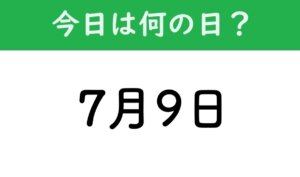「7月10日」。今日は何の日でしょう?答えは「納豆の日」!
「納豆を食べよう!」という関西でのPR運動が始まり
7月10日は、全国納豆協同組合連合会(東京都荒川区荒川)が、1992(平成4)年に全国的な記念日として制定した「納豆の日」。日付は「なっ(7)とう(10)=納豆」と読ませる語呂合わせからこの日になりました。
実は「納豆の日」は、1981(昭和56)年に関西納豆工業協同組合が、関西での納豆の消費の拡大を狙い、発案したのが始まりと言われています。そういえば、「関西人は納豆が嫌い」とか「関西では納豆はあまり食べない」という話を割と耳にします。発酵食品の代表である「納豆」は、もともとは関東より北の米作地帯で作られ、雪の深い季節に魚などに代わるタンパク源となっていました。気候が温暖で瀬戸内海などから魚がいつでも手に入る西日本では、そもそも納豆を作る習慣がなかったことが「納豆を食べない」と言われる所以になっているようです。
「納豆」という名前になった由来は、肉食が禁じられていたお坊さんたちが「お寺の納所(台所)で大豆を原料に作るから」とか、「煮た豆を神棚にお供えしたら、しめ縄に付いていた納豆菌と結びついて納豆になったことから、神に納めた豆=納豆」という説などさまざまあります。
全国納豆協同組合連合会のHPによれば、「納豆」という語句が記録として出てくるのは、平安中期の儒学者・藤原明衡の『新猿楽記』に好きな食べ物の1つとして「塩辛納豆」が記載されているのが最初だそう。