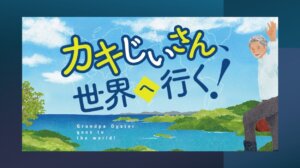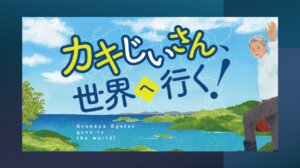ガレキだらけの海辺の街にともった「希望の筏」
9月はじめ、再び益田先生がやってきて、海にもぐりました。
「キヌバリがどんどん増えています。数えたら九百匹はいます。餌が多いから、みんなニコニコしていますよ」
さすが魚の心理学者ですね。
お盆が過ぎると海に筏が浮かび始めました。塩水を被った農地は塩害でしばらく作物を栽培することはできませんが、カキは海(塩水)で育つ生物ですから、塩害はありません。海さえきれいになれば、養殖は再開できるのです。
からっぽになった海に、つぎつぎ筏が浮かび、元の風景が戻ってきたのです。陸側はまだあちこちにガレキの山が残っていて、復興はいつのことだろうとため息が出るのですが、整然と筏が並びだすと、風景が一変してきました。
海辺で暮らす人々にとって、それは希望の風景です。
でも、筏を浮かべても、カキの養殖をするには、カキの種苗が必要です。はたして、種苗はどこに残っているのだろうか……と心配していると、宮城県石巻市の万石浦の種ガキ屋、末永さんから連絡がありました。末永さんとは、1947年(昭和22年)の水山養殖場の創業以来、親子3代にわたるつきあいで、60年以上もカキの種苗の供給を受けています。
末永さんは、
「昨年とったカキの種苗が、津波に流されないで湾の奥の方に残っています」
と言うのです。そして末永さんのところから、トラックに積まれて、次々とカキの種苗が届きはじめ、浜は急に忙しくなってきました。
そのころには、小学校の校庭に仮設住宅が建ち、被災した方々はそこに移り住んでいました。でも、職場はまだまだ復活していません。手持ちぶさたの生活が続いていたのです。
カキ養殖の同業者も、あまりにも被害が大きく、再出発をあきらめようとする仲間も出始めたのです。一人ひとりでは復興は困難でした。そこで、我が家の長男、哲が中心となり、しばらく協業のかたちで、この難局を乗り切ろう、という相談がまとまったのです。
仕事が始まると、人手が必要です。そこで仮設住宅に住んでいる人たちに、
「仕事を手伝ってくれませんか」
と声を掛けてみたのです。すると、20人も来てくれました。こうして、ロープに種苗をはさむ「種はさみ」が始まったのです。