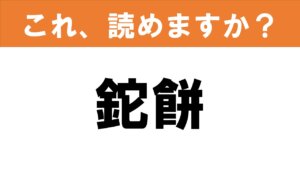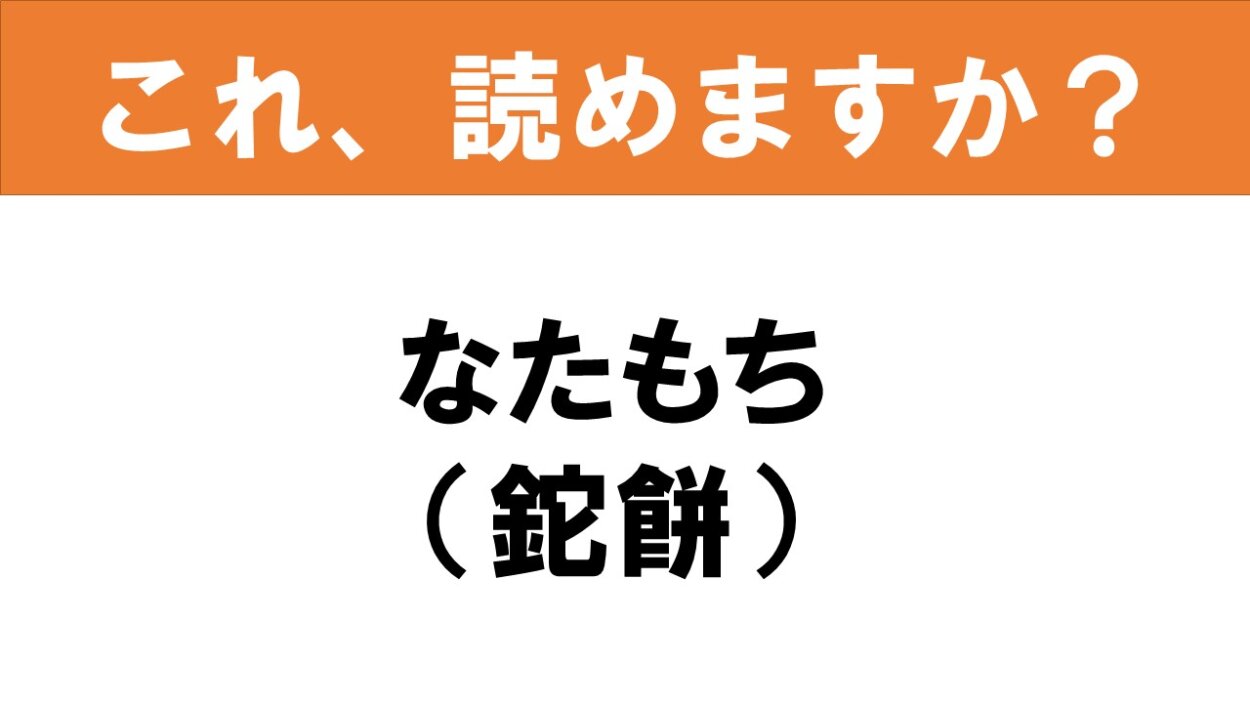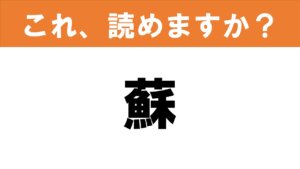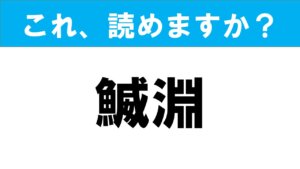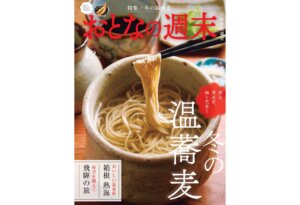■難読漢字、食べ物編の正解はこちら
正解:なたもち
鉈餅は、日本各地に伝わる伝統的な餅菓子の一種で、とくに静岡県遠州地方や北九州などでは、節分や年中行事に合わせて作られてきた郷土食です。
地域によって作り方は異なりますが、基本的にはもち米を蒸し、杵と臼でついて餅状にし、きな粉や砂糖、塩をまぶして仕上げるのが一般的です。
名前は文字通り「鉈(なた)」の形に由来するとされます。鉈とは、山仕事や農作業に使われる刃物の一種で、古くから生活に欠かせない道具でした。
伊豆大島では、嫁入り道具のひとつとして鉈を持参したという伝承も残されており、生活道具以上の象徴的な意味を持っていたことがうかがえます。
北九州では、12月13日の奉公人の交代日に「鉈ナゲ」と呼ばれる行事が行われていたという記録もあります。
このような鉈への特別な思いは、ほかの地域にも受け継がれており、餅を鉈の形に整えて作る風習が一部地域に残っています。
また、鉈の「切る」「断つ」という象徴的な意味は、災厄を断ち切る願いにつながり、鉈の形を模した餅には「鬼や厄を断つ」という思いが込められていたとされます。そうした意味を持つ鉈餅は、無病息災を祈る食べ物として各地に受け継がれてきました。
【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる? 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!