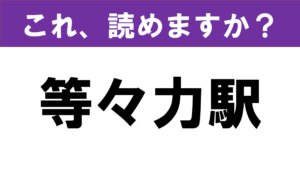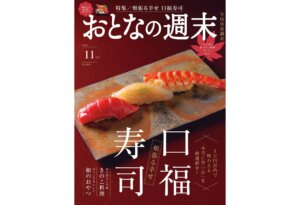この連載では、名古屋めしをはじめ、実際に食べてみて本当に美味しかったものや、名古屋のグルメ事情について、好き勝手に書き綴ろうと思っている。 記念すべき第一回目は、この時季に食べたくなる「ひつまぶし」。今や名古屋エリアのほとんどの鰻屋で食べられるが……。

「ひつまぶし」から垣間見える職人たちの葛藤/名古屋エリア限定グルメ情報(1)

皆さんは、名古屋に対してどのようなイメージをお持ちだろうか? 日本の三大都市の一つとはいえ、大阪と比べれば田舎であることは火を見るよりも明らかだ。都会にしては中途半端なところがツッコミやすいのか、ネット上では散々disられまくっている。 名古屋バッシングは、今はじまったわけではなく、ひと昔前はもっとヒドかった。名古屋の食文化は、“ゲテモノ食い”と評され、名古屋人は、「名古屋名物自虐史観」に陥っていたのである。 風向きが変わったのは、21世紀を迎えたころ。2005年の愛知万博を目前にメディアはこぞって味噌かつや手羽先、ひつまぶしなどを紹介したのだ。おかげで名古屋人は、すっかり自信を取り戻し、胸を張って名物を自慢できるようになった。さらには「名古屋めし」という言葉も生まれた。今や名古屋駅の地下街は、「名古屋めし地下街」と化し、観光のキラーコンテンツとなっている。 この連載では、名古屋めしをはじめ、実際に食べてみて本当に美味しかったものや、名古屋のグルメ事情について、好き勝手に書き綴ろうと思っている。


見ての通り、ひつまぶしは鰻の蒲焼きを細かく刻んである。せっかく丹精込めて焼き上げた鰻を刻んでしまうことに、職人として葛藤があったのではないかと私は推測する。しかし、メディアで他店が紹介されるのを見て、ひつまぶしを出すようになったのだろう。 名古屋めしのなかには、古くからの習慣や伝統に縛られていないものが多い。だからこそ、「邪道だ!」とバッシングされるのだろう。私は逆にそこが名古屋めしの魅力だと思っている。
永谷正樹(ながや・まさき) 1969年生まれのアラフィフライター兼カメラマン。名古屋めしをこよなく愛し、『おとなの週末』をはじめとする全国誌に発信。名古屋めしの専門家としてテレビ出演や講演会もこなす。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。