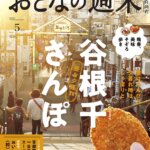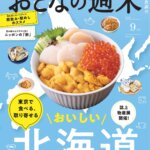日本のお茶といえば煎茶ですが、昨今つとに注目されているのが和の〈烏龍茶〉と〈紅茶〉なんです。企画巻頭では、和烏龍茶作りに力を入れる茶農家のルポからスタート。そのふくよかでやさしい味わいや香りまでもが届きますように!
自然にあふれた春野町で生まれる宇野さんの「ウーノン茶」『うの茶園』@静岡・春野町
農薬を使わず、肥料をなるべく減らし、自然の力に任せて育てている。茶畑を管理することは集落の景観を維持することにもなっている。
手で確かめて香りを引き出す
車から降り立つと、しんとした冷たい空気に体が包まれた。山肌に広がる茶畑が見える。今回訪ねたのは約30年前から集落全体で有機栽培が行われている茶産地、静岡の春野町だ。標高400メートルほどの山間地にある。
ここで烏龍茶ならぬ「ウーノン茶」を作っているのが『うの茶園』の宇野大介さん。早速、お茶を作る茶工場へと案内してもらった。古民家を改築した温かみのある空間に、製茶用の機械が並んでいた。「煎茶と、烏龍茶や紅茶の違いは、茶葉の発酵の有無と、その度合いの違いなんですよ」と宇野さん。

多くの煎茶は茶葉を蒸気で蒸らして発酵させず、収穫後すぐに酸化酵素の働きを止める。対して、烏龍茶や紅茶はしばらく茶葉を空気に触れさせ、酵素を働かせることで香りを生む。その発酵が浅いと烏龍茶、深いと紅茶になる。
茶葉の収穫は朝9時から開始。烏龍茶作りは、収穫後、茶葉をザルに広げ、時折発酵を促すために揺らす。ガサガサ……と夜通し続けるうち、「甘いフルーツのような香り」が立ちのぼる。そのタイミングで茶葉を釜炒り機に投入し、発酵を止める。茶葉の水分が程よく抜けるのは翌日の早朝。約1日かけてようやくお茶が出来上がる。手間はかかるが、「人の手でしか作れないものがあると思います。香りと手触りを確かめながら作っています」と力強く語る。
ひと通り工程を教えてもらったあと、1日で2キロしか製造できないという、貴重な「手摘みウーノン茶」を淹れていただいた。口にするとうっとりするような華やかな香りと甘みが、長く続く。どこか日本茶らしい旨みもある。二煎目、三煎目もそれぞれ違った香りで、注ぐたび茶葉が大きく開く様子にも惹き込まれてしまった。