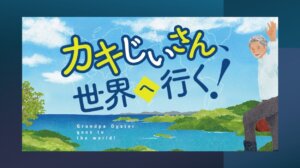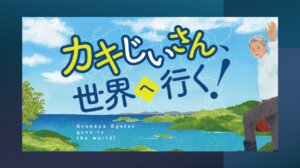母の死
一夜明けて、朝日の中に見えてきた光景は忘れることができません。
湾をとりかこむように海辺に建っていた家が、一軒もないのです。養殖場の作業場と事務所は、土台だけ残して消えていました。残っているのは、コンクリートの水槽だけです。
水槽を取り囲んでいる鉄骨の建物は、見るも無残に折れ曲り、ガレキの山となっています。体験学習のためにつくった40人乗りの木造船「あずさ丸」も、姿を消していました。
何より残念だったのは、いけすの上に建っていたわたしの書斎小屋が流されたことです。22年間続けてきた、漁師による森づくり「森は海の恋人運動」の記録がそこにあったのです。特に体験学習でやってきた子どもたちの感想文を失ったことは、今でも残念でしかたがありません。1万通近くあり、整理して本にしようと思っていたからです。がっかりしたわたしの姿を見て、ご婦人たちが声をかけてきました。
「カキじいさんらしくないですよ」と。
朝ご飯をつくらなければなりません。台所が問題でした。プロパンガスのレンジからIH調理器に換えていたのです。停電になるとIH調理器はただの鉄の板です。ご婦人たちはレンガを積んで即席のかまどをつくり、山から枯れ木を集めてきて、もうご飯を炊きはじめています。
あっという間におにぎりができ、味噌汁や焼き魚も出てきました。この22年間「森は海の恋人運動」でおおぜいのお客さんをむかえることが多く、百人単位の食事をつくってきたので、チームワーク抜群です。
気がかりなのは、街の施設にいる母の安否です。電柱が全部倒れていて、道をふさいでいます。舞根峠を越えて街まで歩いて行こう、と次男の耕とでかけました。太平洋戦争の末期に、1歳半だったわたしを背負って上海から日本に帰りついた運の強い母です。もしかしたら助かっているかもしれない、と自分に言い聞かせました。
母の入所している施設が見えました。2階の窓は割れ、1階は波が突き抜けめちゃくちゃに壊れています。看護師さんに母の安否を問いますと、下を向き、「残念です」と告げられたのです。津波で体が水浸しとなり、低体温症で息を引き取ったそうでした。この施設で暮らしていた方の約半数が亡くなったのです。終戦時は20歳だった母も、あのときは93歳。あの大津波に立ち向かうのは無理だったのです。
母は椿が好きでした。耕は椿の花柄の手ぬぐいを持参していて、そっと顔にかけてあげました。思っていたより柔和な死に顔であったことが、ただ一つの救いでした。