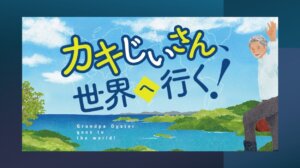カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。
そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く!』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。
「カキをもっと知りたい!」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。
これからあなたをカキの世界へ誘おう。
連載24回「宮城県・気仙沼のカキ、ホタテ、アワビ、ウニ「32億円分の水揚げ量」に影響…ロシア・中国・日本の「共同研究で判明」した新事実とは」にひきつづき、親潮に乗って北三陸沖にやってくるロシアの流氷の出発点を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。
【前回まで】
北海道大学の白岩孝行教授は、カムチャッカ半島の氷河を調査する中で、黄砂に含まれる鉄分が北の海の青魚(イワシ、サンマ、サバなど)の漁獲量に影響していることを発見した。海洋化学者・松永勝彦との研究で、気仙沼湾の豊かな海産物も川が運ぶ鉄分に支えられていると判明。さらに、森林由来のフルボ酸鉄にも注目し、ロシア・中国・日本の共同研究「アムール・オホーツクプロジェクト」を立ち上げた。氷の研究から始まった探究が、陸と海をつなぐ鉄の循環解明へと広がっていく。
「アムール・オホーツクプロジェクト」
わたしは北海道大学の白岩孝行先生の「アムール・オホーツクプロジェクト」を知って、さっそく地図を広げていました。じつはわたしは、ホタテじいさんでもあります。北の海の貝であるホタテ貝の養殖に、ずいぶん南である宮城県の海で初めて成功したのです。もう60年も前、19歳の時でした。そのため北海道を旅し、冬のオホーツク海で流氷を見ていました。北海道の漁師さんから、「流氷によって運ばれる養分が、ホタテを育てている」という話は聞いていました。
そしてロシア、中国、日本の学者を束ねたアムール・オホーツクプロジェクトの5年にわたる研究で、すごいことがわかったことを知りました。
ロシアと中国の国境を流れるアムール川からオホーツク海に流れ込む水の量は、平均で毎秒1万トン以上。これは東京ドームを2分間でいっぱいにする量だそうです。アムール川の水に含まれる鉄分の濃度は世界の河川の平均的な濃度より2けた多いことが分かりました。
アムール川から流れ出す鉄分の10パーセントはフルボ酸鉄の形となり、オホーツク海の表層を運ばれ植物プランクトンを育み食物連鎖が続きます。大川が流れ込む気仙沼湾で調査された松永勝彦先生の研究は、こんな大きなスケールでもちゃんと裏付けられたのです。
90パーセントの鉄はアムール川河口域で海水が凍るとき、塩分濃度が高く重くなった海水に取り込まれ、200メートルから500メートル沈むといわれています。そして、「東サハリン海流」に運ばれ、千島列島に近づきます。地球は自転しているので、すごい勢いの海流になるのです。千島列島のウルップ島とシムシル島の間にあるブッソル海峡からすごい勢いで飛び出します。こうして、鉄は、三陸沖まで届くのです。鉄の分析のチームは、わたしと気仙沼湾で調査に参加した西岡純先生です。