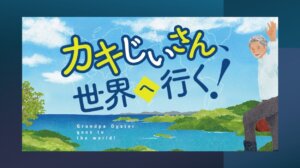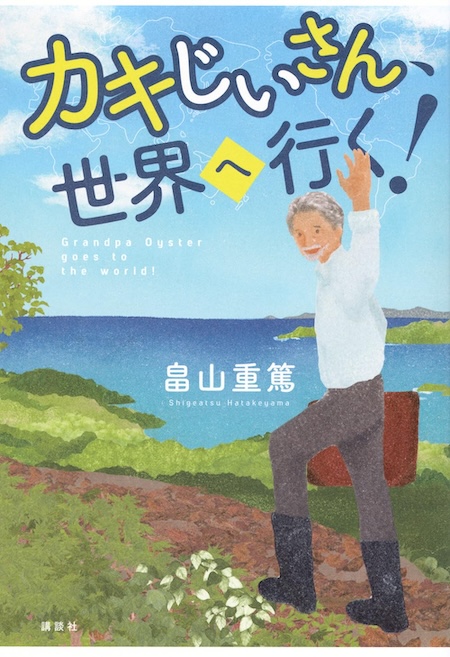ロシアの大森林、アムール川、オホーツク海、ブッソル海峡、北太平洋、三陸沖、親潮とのつながりが見えてきました。今まで、水産学者は、海しか見ていませんでした。林学者は森林を、地質学者は土や岩石を、気象学者は風や雨や空気の流れを、といった具合でした。
白岩先生は地理学者です。地理学者は、このような学問を束ねる立場にあったのです。さらに、海の植物プランクトンの繁殖にもっとも大切な成分である、鉄分の知識をプラスすると人類の未来に関わるような大切なことが見えてくるのです。近ごろ学問の世界では地理学は重要視されない傾向にありました。でも白岩先生の「束ねた研究」で脚光を浴びることになったのです。
地球の70パーセントは海ですよね。じつは海の植物プランクトンの光合成の力は、全陸地の植物の力と、ほぼ同じであることがわかってきたのです。地球温暖化解決の鍵は、海の植物プランクトンなのです。
アムール川流域の森林を見たいと思っていました。思っていると、ある日突然実現するものです。わたしの経験則です。
武蔵野市からの手紙
2014年(平成26年)、東京の武蔵野市役所から手紙がきました。武蔵野市はロシアのハバロフスク市と長い交流があったのです。日本とロシアを行き来する渡り鳥の共同研究をきっかけに、1991年より武蔵野市とハバロフスク市の交流が始まりました(2009年にNPO法人「むさしの・多摩・ハバロフスク協会」となりました)。太平洋戦争で捕虜になった日本兵の収容所があった地で、多くの人が亡くなり、お墓があるところでもあります。武蔵野市からも墓参団が訪れていたのですが、ある時、こんな話を聞いたそうです。
アムール川流域の森には、アムール虎が生息しているのですが、激減しています。虎はイノシシを食べています。イノシシの餌はチョウセンゴヨウという松の木の実で、もっとも実がなるのは樹齢150年から170年の木です。
ハバロフスク地方を代表するこの木は建築材としてすぐれていて、どんどん伐採されています。輸出先は日本だというのです。植林をしたいのですが、ロシアは広大で、植林するという考えがうすく、苗木のつくり方から考えねばなりません。
そこで武蔵野市は苗木づくりを補助してきました。やっと苗木ができ、植林祭をすることになりました。なんと、わたしに参加してほしいとのことです。また、ロシア極東最大級の太平洋国立大学で講演をしてほしいとのことでした。
…つづく<やっぱり日本人は凄かった…三陸のカキじいさん「森は海の恋人」がロシアで「ハラショー」と絶賛されたワケ>では、ロシアのハバロフスクの植樹祭に招かれたカキじいさんの現地で驚いたことを明かします。
連載『カキじいさん、世界へ行く!』第25回
構成/高木香織
●プロフィール
畠山重篤(はたけやま・しげあつ)
1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』(講談社)で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』(文藝春秋)で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい:命と地球をはぐくむ「鉄」物語』(小学館)で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』(北斗出版)、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』(ともに文藝春秋)などがある。2025年、逝去。