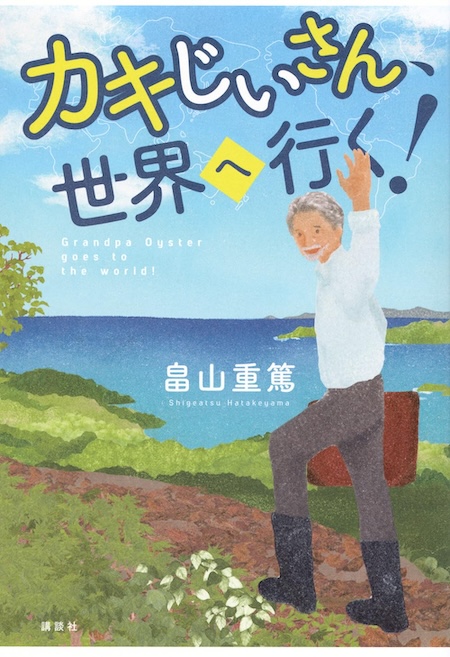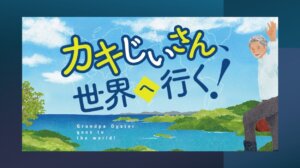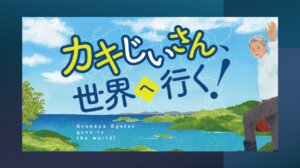「ロシア・中国・日本」の共同研究が動きだした!
白岩先生は、黄砂の中に含まれる鉄分が、青魚の漁獲量に大切であることを理解します。でも、黄砂が飛ぶのは主に春先です。夏、秋、冬の鉄分はどこからくるのでしょう。海の生物と鉄分研究の第一人者、北海道大学の松永勝彦先生は、気仙沼湾の生物生産と、湾にそそぐ大川が運ぶ鉄分の関係を調べあげていました。
気仙沼湾で生産されるカキ、ホタテ貝、ホヤ、ワカメ、コンブ、アワビ、ウニなどの水揚げ金額は、年間約40億円です。松永先生は、数字におきかえて計算してみました。すると、40億円の80パーセント、32億円分は、大川が運ぶ鉄分を中心とする養分のおかげであることがわかり、発表していたのです。川ってすごいでしょう。
白岩先生は、森林の腐葉土で生まれるフルボ酸と結びついた鉄についても学びました。わたしたちが行っている「森は海の恋人運動」にも心を動かされました。
青魚から黄砂の故郷、広大なゴビ砂漠を考え、気仙沼湾に流れる、たった30キロメートルの大川から、ロシアと中国の国境を流れる全長約4,400キロメートルのアムール川を想像しました。氷河の研究で登っていたカムチャッカ半島のウシュコフスキー山頂からオホーツク海をながめると、かすかに千島列島が見えます。その先は三陸沖、世界三大漁場ではありませんか。
白岩先生の専門は、自然地理学。海側から陸側までの大自然を上から見渡せるのは地理学者です。国境をまたいでの学者のネットワークも地理学者ならではのものです。
こうして、ロシア、中国、日本の学者をたばねた「アムール・オホーツクプロジェクト」が動き出したのです。このプロジェクトのキーワードは、アムール川から流れてくるフルボ酸鉄の測定です。海水1リットル中に含まれる鉄分量は、わずか10億分の1グラムレベルと微量。高度な分析技術が求められます。
分析をするのは誰がいいかと松永先生に相談すると、「西岡純君がいいのでは」と推薦があり、北海道大学低温科学研究所の准教授に迎え入れ、チーフ(責任者)にしたのです。西岡先生は、以前に松永先生が行った気仙沼湾の調査のとき、まだ大学院生でした。面接のとき、わたしと海水をとるサンプリングの経験があることを、白岩先生に打ち明けたそうです。
…つづく『「こんなうまいものがあるのか」…20歳の青年が、オホーツクの旅で《ホタテ貝の刺し身》に感動、その後はじめた「意外な商売」』では、かきじいさんが青年だったころのお話にさかのぼります。
連載『カキじいさん、世界へ行く!』第24回
構成/高木香織
●プロフィール
畠山重篤(はたけやま・しげあつ)
1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』(講談社)で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』(文藝春秋)で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい:命と地球をはぐくむ「鉄」物語』(小学館)で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』(北斗出版)、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』(ともに文藝春秋)などがある。2025年、逝去。