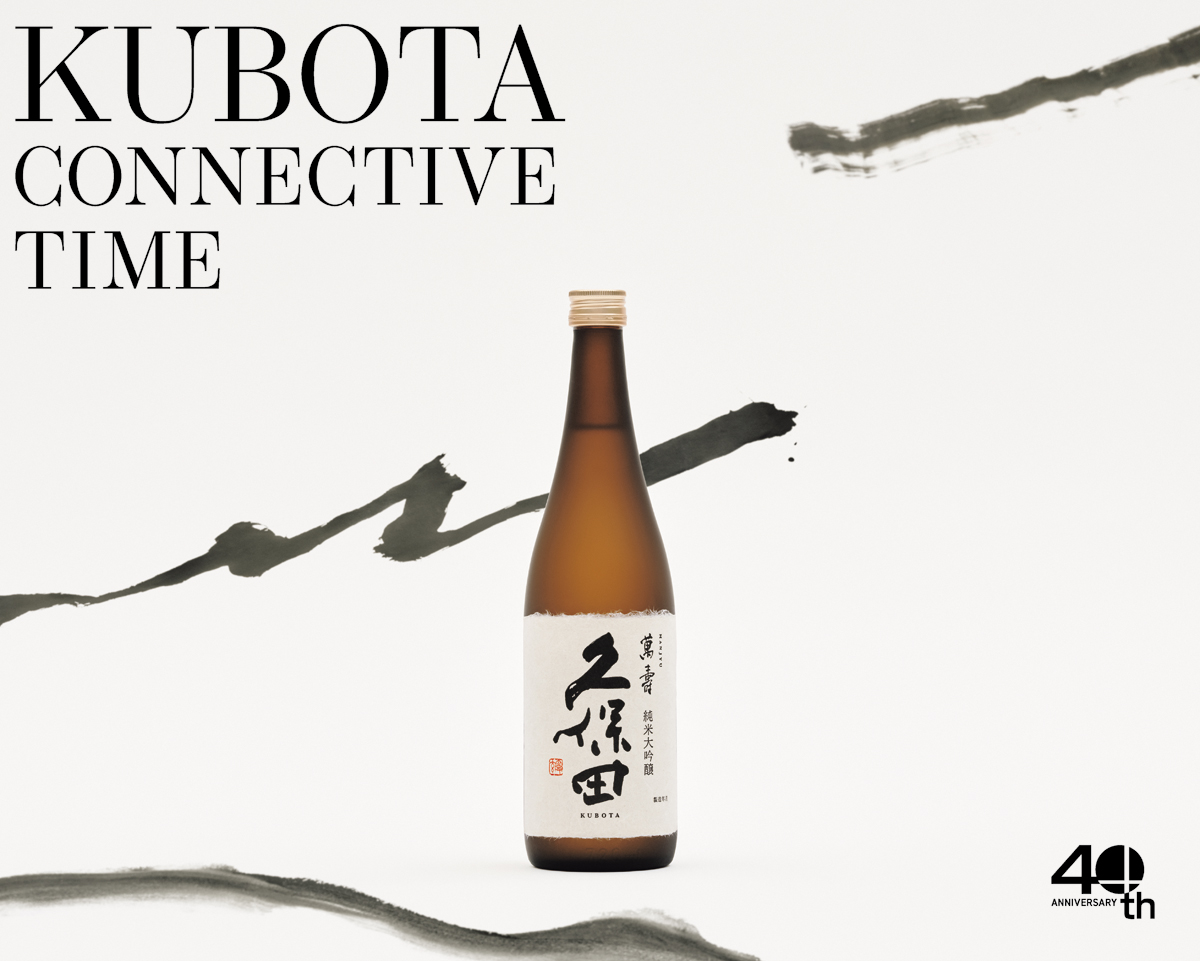2025年で40周年を迎える、銘酒「久保田」。品質本位な酒造りの姿勢はそのままに、多彩な表情を持つ日本酒を展開させていることでも話題です。今回はそんな多種あるなかから、よりいっそう食中酒として深く愉しみたい「久保田」を、グルメなふたりに選んでもらい、熱く語って頂きました。
PR、提供/朝日酒造株式会社
料理とのマリアージュがどこまでも膨らむ食中酒としての「久保田」
朝日酒造が醸す「久保田」は、常に進化する日本酒だ。1985年、新潟県長岡市で誕生以来、品質本位の酒造りを守りながらも感覚を磨き、その淡麗辛口の味に時代を映してきた。“変わりゆく時代にふさわしい挑戦”を続け、今や17種ものラインナップを展開。今回は、なかでも食中酒として愉しみたい「久保田」を、マッキー牧元さんと門脇編集長にセレクトしてもらいました。
マッキーさん(以下マ)「久保田はまず、それぞれの名前がいいね。百寿、千寿、萬寿、と高みを目指す感じにロマンがある。若い時は百寿を飲み、いつかは萬寿、と気持ちを掻き立てられたものです」
門脇(以下門)「そう、階段を上らなきゃ、とね。僕は昔、先輩に連れて行かれた銘酒居酒屋での出合いが最初。千寿の淡麗さと飲み心地に驚いた記憶があって。クオリティが高くキレがある、というのが久保田の揺るぎない印象です」
マ「久保田のキレは、美意識の高さ、美徳とも呼べる信念を感じるね」
門「今回、改めて数々の久保田を試飲してみたけれど、いろいろ合わせたい料理が思い浮かびました」
マ「この歳になり、ある程度酒を嗜んできたからこそ、百寿や千寿の親しみやすい飲みやすさが分かるようにもなってきて。百寿は常温でいぶりがっこに、千寿のクリアな味わいにはタコきゅうやうなきゅうを合わせたい。ワカサギのフライにカボスを搾っても進みそう」
門「柑橘の香りと響き合いますよね。では、僕は穴子の白焼にすだちを添えて、千寿のアテに」
マ「いいね。いっそ、千寿の杯に柑橘を1滴垂らすのはどう? 食中酒としての幅が一層広がるよね」
門「紅寿もまた、食中酒として優秀。口に含むとバナナ香が広がり、クリーム系の料理やグリーンカレーなどのアジア飯にぴったり」
マ「香りが清涼感もあって柔らかだから、料理の邪魔をしない。ココナッツチキンにも合うね。タイ料理で一杯やるのも乙ですよ」
門「萬寿はどうですか。僕はシーフードグラタンで飲みたいなあ」
マ「うん、脂肪分の多い料理に合うね。萬寿でも自社酵母仕込の方は、ミネラル感のある味わいとエレガントな香りが堪らない。ぬる燗で華やかに、燻香やチーズのコクを利かせたイタリア料理と合わせたい。あと、生牡蠣にもいい」
門「賛成! 自社酵母による、熟した花梨のようにウッディで重層的な香りがあって、飲めば、五味のバランスもすごくいいですね」
マ「1本で食事全般通して飲める」
門「牡蠣の昆布蒸し、ホタテのポワレ、巨峰とブッラータチーズ……合わせたい料理が尽きません。僕の故郷・松江の郷土料理“スズキの奉書焼”ともシンクロしそう。これぞ、食中酒としての久保田の象徴的な存在だな、と」
マ「一方、純米大吟醸は、料理なしでも完結している感すらある。白身魚のお造りや塩でいただく十割蕎麦といった、できるだけシンプルな料理と合わせたいですね」
門「同感です。味わいはシャープでモダン。実に完成度が高い。上質な塩を舐めながら飲みたいくらい。このお酒の清冽さと純粋さを、せりやわさび菜のおひたしみたいな清々しいものと一緒にいただいて、キレイな人間になりたいです(笑)」
マ「じゃあ、山に行って清流の横で飲みますか。森林の香りとのマリアージュもいいと思うよ」
門「紅寿を飲んで頭に浮かぶのが亜熱帯の風景なら、こちらは山。我々、この純米大吟醸は、どこまでも青く清らかにいきたいわけです」
マ「この酒をつゆ代わりに、十割蕎麦をすするのも粋。お酒もモダンを追求すると、むしろ日本の原風景にたどり着くのかも。そのストイックさや対峙するという点で、蕎麦と合わせるのは興味深い。そして、そこには久保田が在る、というイメージが浮かびました」
門「食いしん坊はたいてい妄想家で、いい酒は料理の妄想を膨らませてくれる。それは文化の豊かさであり、まさに久保田は文化の香るお酒ですね」