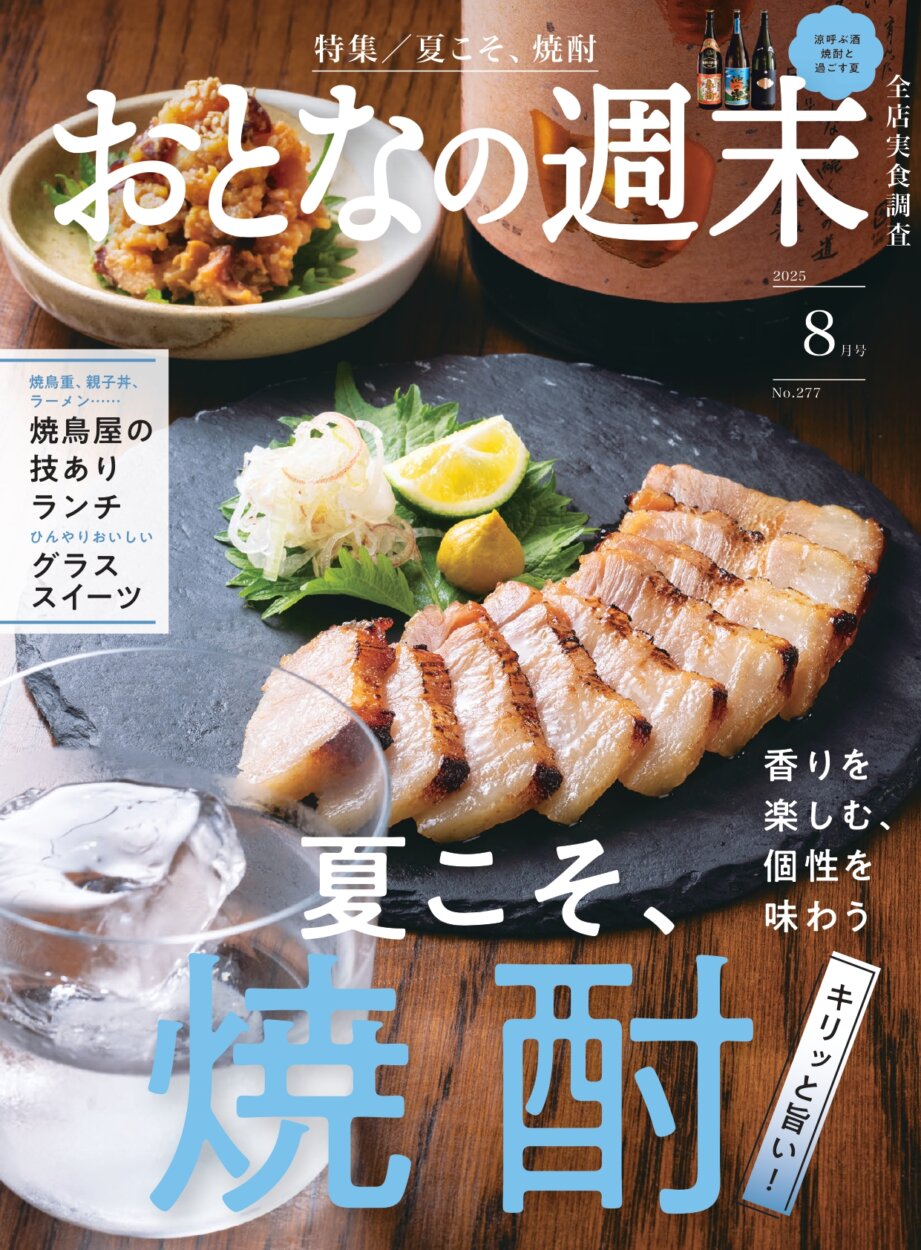今、焼酎が熱い。特に香り系など個性的な味わいの揃う芋焼酎が、居酒屋で家庭でと広く楽しまれている。なぜおいしくなったのか?なぜ個性的な味わいが生まれるのか?その理由を探るべく、鹿児島県霧島市の『中村酒造場』を訪ねた。霧島山系の良質な伏流水、契約農家から仕入れる芋や米など原料はもちろん、石造りの麹室での米麹造りまで。こだわりの“手造り製法”でここにしかない味を醸す。今なお進化を続ける代表銘柄「なかむら」の味わいはなめらかで深い。
記憶や感性に訴えるそのための麹造り『中村酒造場』@霧島市
煉瓦造りの外観が印象的な中村酒造場。明治21年創業、今年で138年になる老舗蔵には、昔から変わらぬ石造りの麹室がある。その場所を6代目の杜氏・中村慎弥さんは「蔵の心臓部」と呼んだ。
「この土地ならではの軸足のしっかりした焼酎を造りたい」。そう考えたときに、継承しかつ突き詰めたいと考えたのが、蔵が昔から大事にしてきた米麹造りだ。
でき上がった焼酎の旨みや味わいの深さ、口当たり。これらは数値化しにくいものだが、それらが飲み手の感性や記憶に訴えかけると考える。そこに関与するのが米麹だ。
「さつまいもと米麹の関係は、お寿司で言えばネタとシャリの関係だと思うんです」と慎弥さん。まず、シャリを突き詰めようというわけだ。目指すべきは繊細でありながら芯のある酒質を生む、美しく力強い麹。