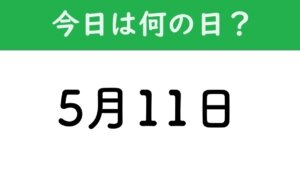第1ホール パー5 意のままにならぬゲーム
その1 パット・イズ・マナー
初期のゴルフで悪天候以上の天敵だったのは!?
残された絵画などから推察すると、ゴルフは18世紀前半までゲームとしての体裁が整わず、どちらかというと委細構わず前進するだけの「クロスカントリー競技」に近いものだった。
とくに7世紀ごろから周辺国と戦い続けて、宿敵イングランドにもうしろ姿を見せなかった勇猛果敢なスコットランドの陸軍が教練の一環として採用した日から、「あるがまま」の思想も定着した。
過酷な気象条件下、兵士たちは喜々として障害物に挑みかかり、絶対に弱音を吐かなかった。ゆえにゴルフではスピードも重要なテーマの一つである。
「ゴルフに携わる者よ、肝に銘じて聞け。コースに身分、地位、肩書きを持ち込むべからず。ゴルフは平等の精神によって成り立つゲームなり」(キングホーンGCの設立憲章より)
「コースは神が創り給うた無垢なる大地、全世界にあまねく在り。われら、ただ旗を立てるのみ」(バリーGCの設立憲章より)
初期の時代、次々に誕生するコースには独自の思想があった。やがて、それらが一つにまとまってゲームの核となり、会則にも明記されるようになった。しかし、いくら旗を立てるのみと言っても、ヒースの中に立ててはパッティングに困る。初期のグリーン造りにもいくつかの条件が要求された。
まず、10人以上の屈強な男が思いっきり地団駄踏めるだけの広さと、勝ったチームが一斉に飛び上がって着地しても穴のあかない丈夫さが要求された。加えて犬の散歩道から隔離された場所であれば一層申し分なかった。当時のゴルフにとって、犬は強風以上の天敵であった。
22人が参加したゴルフの決闘の結末とは?
1769年7月、居酒屋「エッシャーズ・ターバン」にたむろする二つのグループに諍いが発生したときもそうだった。これがよその国なら銃と剣による決闘と相成るが、そこはスコットランド、全員参加のゴルフによって決着がつけられることになった。
いよいよ当日、ブラックヒースの1番ティに集まった両チームの頭数を勘定したところ、なんと22人。それでも各自がボールに目印などつけて、まるでラグビー顔負け、団子状のゲームが開始された。
古くからマッチプレーによる1対1も行われてきたが、日常的には人数問わずの団体ゲームだったことが窺える。
ようやく1774年に公式競技のはしりともいえる「シルバーカップ」開催に際して、最初のルール13ヵ条が誕生、さらに1パーティ4人以下とすることでゲームの流れを良くする知恵も生まれた。
何しろプレーヤーが22人、ティショットだけでも30分が経過する難儀に加えて、随所にトラブルが発生、ルール誕生の5年前とあって裁定に基準もなく、つかみ合い寸前の雲行きが数ホール続いた。
と、いきなり信じ難い事態が起こった。1人のプレーヤーのボールが、あろうことかグリーン横に鎮座していた犬のフンの上にチョンと乗ってしまったのだ。これには両軍選手をはじめ、大勢の応援団もお腹抱えて大爆笑。しかし、その選手からすると笑い事では済まされなかった。
「これは自然の障害物に非(あら)ず。拾って後方にドロップする許可をいただきたい」
彼の申し出に対して、相手チームの主将はニべもなかった。
「何を言う。太古よりゴルフには二つの掟(おきて)が宿るのを忘れたか。その1、己れの有利にふる舞わぬこと。その2、あるがままにプレーせよ。ささ、現状のライを改善することなく、しかもエクスプロージョンによって周囲に迷惑が及ばぬよう、十分注意した上でプレーを続行してくれ給え」
セントアンドリュースをはじめ、各地に点在したコースは市民広場の間借りだった。ゆえにペットの往来も激しく、連中にとって平坦な芝は絶好のトイレ、悲喜劇が絶えなかった。
さて、囂々(ごうごう)の野次の中、くだんの男は何回となく小さな素振りをくり返したあと、いよいよフンと対峙した。全員固唾(かたず)をのんで見守る緊張の一瞬、クラブが小さく振られた。
次の瞬間、天地が裂けたかと思うほどの喚声が沸き上がり、全員その場にひっくり返って手足バタバタ、笑って笑って悶絶寸前。くだんの男もしばし呆然と立ちすくんでいたが、やがてクラブを放り投げると一座の中に飛び込んで、こちらも笑って笑ってケイレン状態だった。そう、確かにデリケートなアプローチは実行された。ところがボールはヘッドに密着して前には飛ばなかった。
この珍事によって、両者のわだかまりが氷解したこと言うまでもない。ゴルフはムキになって戦うものに非ず、勝負より友愛が似つかわしいゲームだと、また一つ学んだ次第である。