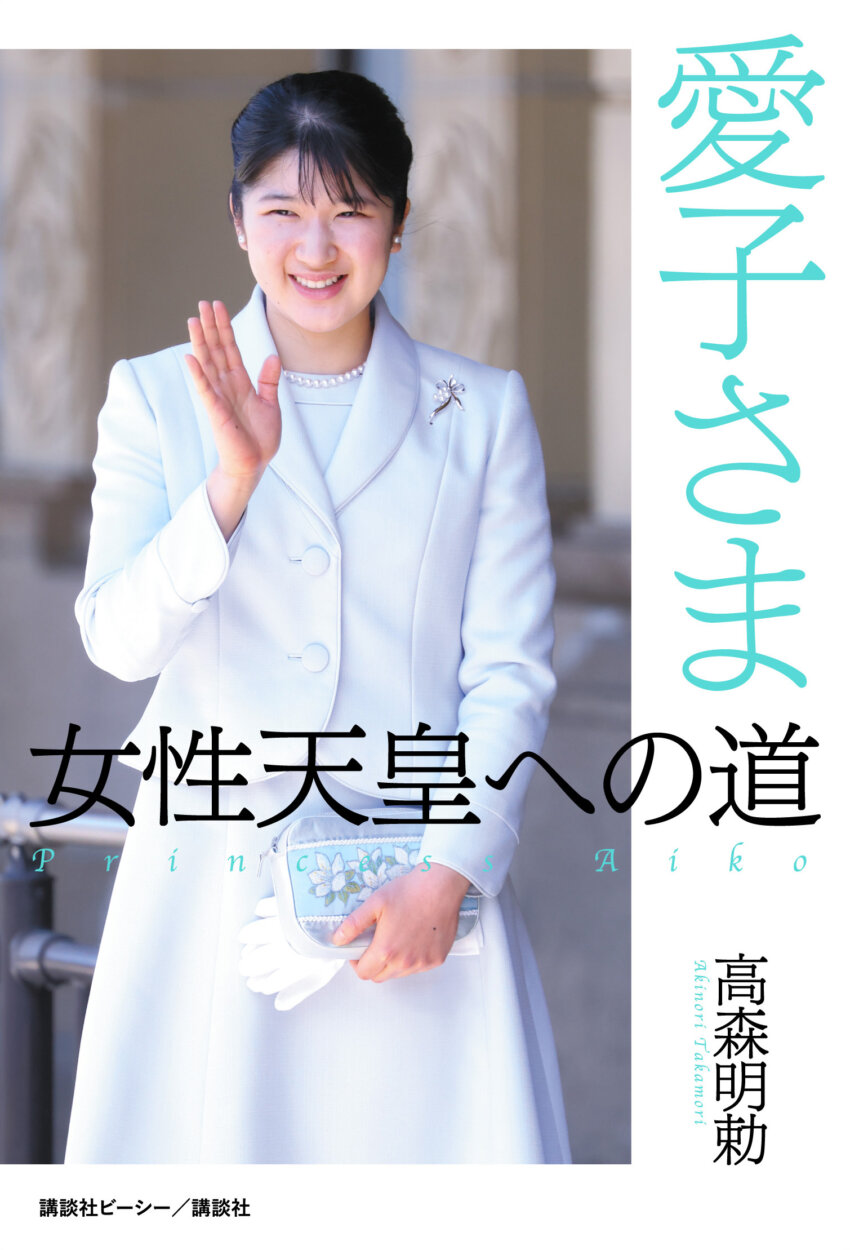春分の日、御所では「牡丹餅(ぼたもち)」が出される。春分は先祖を祀るお彼岸の日であり、皇居では「春季皇霊祭の儀」「春季神殿祭の儀」が執り行われる。「牡丹餅(ぼたもち)」は、春のお彼岸のお供え物なのだ。そうして、秋分の日のお彼岸には、御所において「萩の餅(おはぎ)」が出される。一般の家庭でも楽しむこの和菓子だが、どこが違うのだろう? 今回は、春と秋のお彼岸にちなむ和菓子の物語である。
「ぼたもち」は春の「牡丹」、「おはぎ」は秋の「萩」から名づけられた
春のお彼岸の中日である「春分の日」のご昼餐のとき、両陛下には「牡丹餅(ぼたもち)が出される。お皿に小さく丸められた餡餅ときな粉餅が盛り合わされ、小豆色ときな粉のほんのりとした黄色がいかにもおいしそうだ。一般の家庭で楽しむ「ぼたもち」と変わらない姿である。
半年後、秋のお彼岸の中日には、「萩の餅(おはぎ)」がご昼餐時に出される。こちらも餡餅ときな粉餅の盛り合わせである。実は春のお彼岸のお供え物である「牡丹餅(ぼたもち)」と「萩の餅(おはぎ)」は、名前こそ違うけれど、実は同じ和菓子。春に咲く牡丹と、秋に咲く萩の花にちなんで名づけられている。牡丹と萩は、ともに美智子さまが愛されている花である。
通常、春牡丹が咲くのは5月ごろで、白や淡紅、黄や紫といった色とりどりの花の豪華さから「百花の王」「百花の神」と称される。原産地は中国で、奈良時代の聖武天皇のころに渡来したといわれている。
美智子さまは、牡丹の花をお歌に詠まれている。
牡丹
皇居奉仕の人らの言ひし須賀川の園の牡丹を夜半に想へる
(天皇陛下御誕辰御兼題/昭和57年)
秋の萩は8月から10月ごろに、赤紫の小さな花を枝いっぱいに咲かせる。名前の中に「秋」の字が残っているほど、萩は古くから日本人に愛されてきた秋を代表する花である。『万葉集』の中で詠まれている花のうち、もっとも多いのは萩だという。
美智子さまは、萩をこのように歌に盛り込まれている。
萩
遊びつかれ帰り来し子のうなゐ髪萩の小花のそこここに散る
(昭和45年)
風になびき乱れた髪のあちこちに、萩の赤紫の花びらがついている。子どもたちのはじけるような笑顔が目に浮かぶようだ。