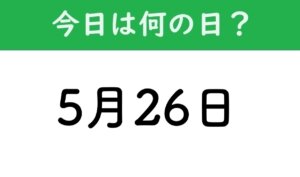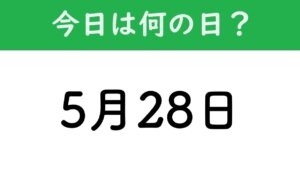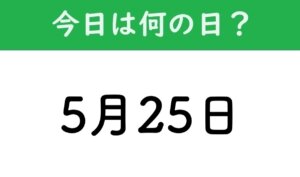物流を支えるインフラとしてさらに進化する日本の高速道路
経済成長率年平均で約10%といわれた高度成長期(1955〜1973年頃)には、東京と関西をつなぐ国道1号線の貨物輸送量も急増し、慢性的な渋滞が発生していたといいます。東名高速道路が建設されたのは、もっと大量にもっと速く、貨物の輸送ができる自動車専用道路が必要とされたからでした。
さらに2012年には「新東名高速道路」の一部が開通しました(2027年全線開通見込み)。NEXCO中日本の「新東名高速道路の開通とその効果」という資料によれば、「新東名は、現東名より山側を通過(由比地区では約 7 キロメートル山側を通過)しているため津波の影響を受けにくく、また、東海地震の想定震度が比較的低い山地部を通過している。新東名と現東名が相互に行き来できるダブルネットワークとなることで、災害や事故でどちらかが通行止めになっても、もう片方が通行可能となっていることでその影響が最小化され、東西交通の確保という信頼性が大きく向上することとなる」とされています。
年々増加する物流を支えるインフラとしてはもちろん、有事にも活躍する道路として期待されています。2011年に発生した東日本大震災のときには、西日本から被災地に向かう救急車両が新東名高速道路を使って移動したそうです。