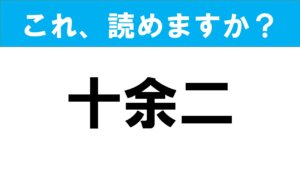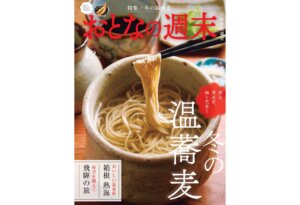森の京都・亀岡市は昔より麦畑が広がる場所。市内を流れる保津川沿いは扇状地で水捌けがよく、ビールの原料となる二条大麦の栽培が盛んだ。全国的には栃木県や佐賀県、福岡県などのようにビール用大麦の一大産地ではないものの、大手のビールブランドなどとの契約もあって、亀岡産の原料を使ったビールを楽しむことができる。
与謝野町でホップ栽培
近年、福知山市の隣になる与謝野町ではホップの栽培も行われており、ビールの主原料である大麦、ホップ、そして京都が誇る良水でつくられるオール京都のビールとなれば、ぜひ飲んでみたいものである。

ちなみにビール用の大麦栽培を関西で初めて行ったのは京都で、現在の西京区あたりだそう。それより以前の1877年ごろには、京都舎密局(きょうとせいみきょく)でビール醸造が始まっている。
京都舎密局とは、東京奠都後、京都の産業振興を目的に京都府が設立した理化学研究所のこと。ドイツ人科学者ゴッドフリード・ワグネルなどの学者を迎え、京都の伝統産業である陶磁器、織物、染色の改良、石鹸の製造、鉄砲水(ラムネ)の製造、七宝、ガラスの製造など京都の近代産業発達に大きな役割を果たした。
その中にビールの製造も含まれていたわけだ。そしてビールの醸造所はなんと清水寺の境内に建設されている。清水寺・音羽の滝そばの水源でビールの醸造に適した水が発見されたのだとか。清水寺産ビール(?)なんて、ぜひ飲んでみたかった一杯だ。