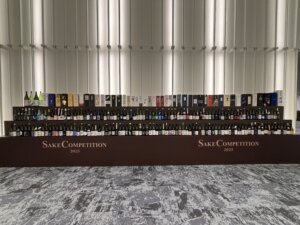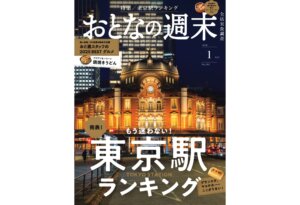広告収入が150億円を突破し、邦画の実写歴代2位となる大ヒット映画『国宝』は、歌舞伎という伝統芸能に生きる役者たちの宿命と覚悟を描き、多くの観客を魅了しました。今回ご紹介するドキュメンタリー『伝統と革新 蒼き想い ~八代目尾上菊五郎 六代目尾上菊之助 重責と覚悟の120日~ ノーカット完全版』は、その“リアル版”とも言える迫力の一作です。父・八代目尾上菊五郎(本名:寺嶋和康)と、息子・六代目尾上菊之助(本名:寺嶋和史)の同時襲名と、過酷な修業の日々に密着。歌舞伎の血脈と継承、その裏側まで徹底的に追います。
約300年続く名門・音羽屋の系譜
歌舞伎は連綿と続く伝統の芸。その中でも、尾上菊五郎の屋号「音羽屋」は江戸中期まで遡る屈指の名門です。二代目以降、大名跡は受け継がれ、写実的な演技で革新をもたらした五代目、そして昭和から平成にかけて第一線で活躍し「人間国宝」となった七代目へと至ります。
その七代目を父にもつ八代目は、古典の精髄を大切に守りながらも現代的な解釈を取り入れ、歌舞伎の新たな可能性を切り拓いてきました。女方・立役いずれにも挑み、話題作にも積極的に取り組んできた存在です。そして今、その名跡を共に背負うのが息子・六代目尾上菊之助。舞台を降りればゲームが好きな、ごく普通の小学6年生という素顔も併せ持ちます。
映画と現実が交差する瞬間
映画『国宝』に登場する演目『京鹿子娘道成寺(きょうがのこむすめどうじょうじ)』は、音羽屋が大切に受け継いできた実在のレパートリー。スクリーンで見た美と魔性の世界が、現実の舞台にそのまま息づいている――そんな感覚が、作品を通して蘇ります。番組でも同じ演目が紹介され、映画のシーンと重なります。更に番組内では現在の女形の最高峰である人間国宝・坂東玉三郎氏のインタビューもあり、同じ時代に生きる役者からの継承を伝えているのは感慨深いものがあります。
八代目尾上菊五郎は映画『国宝』について、次のように語っています。
「映画は喜久雄の『才能』と俊介の『血筋』の対比をドラマチックに描きます。歌舞伎は血筋でつながる部分はもちろん多いですが、私は『守る』と『見出す』の連続で伝承されていると考えています」(朝日新聞 2025年9月17日朝刊)
密着カメラが捉えるのは、舞台の華やかさの裏側にある稽古場での厳しい言葉と深い愛情。弱冠11歳で菊之助を襲名した息子に、父は容赦なく指導を重ねます。その背後には「伝統を絶やさぬためには、芸を自分のものにせねばならない」という揺るぎない信念が見えます。映画が描いた“役者の宿命”が、ここでは父子の実像として立ち上がります。