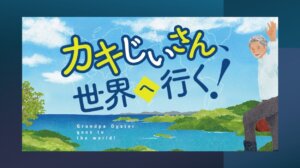カキが旨い季節がやってきた。衣はカリッと身はジューシーなカキフライ、セリがたっぷり入ったカキ鍋、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。レモンをちょいと絞ればなおさらよい。うーん、旨い!
そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く!』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。畠山さんは「カキ養殖には、海にそそぐ川の上流の森が豊かであることが必須」と、山に植林する活動への取り組みでも知られている。
「カキをもっと知りたい!」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。これからあなたをカキの世界へ誘おう。
連載22回「日本を訪れた「ルイ・ヴィトン一族」が「気仙沼産のカキ」に漏らした、感動の一言…まさかこんな共通点があるなんて」にひきつづき、親潮に乗って北三陸沖にやってくるロシアの流氷の出発点を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。
氷の研究者
三陸沖は陸からずいぶん遠いです。宮城県の海に注ぐいちばん大きい川は、北上川です。岩手県の盛岡市の北が源流で、宮城県の石巻湾などに注いでいます。全長約250キロメートル、大きな川ですよ。でも三陸沖といいますと、気仙沼から約650キロメートル先の太平洋までを指します。とてつもなく広い太平洋です。北上川の鉄分が届くとは思えません。鉄はどこからくるのでしょうか。
2009年ごろ、北海道大学低温科学研究所の白岩孝行先生と出会いました。専門は総合地球環境学と自然地理学。とくに氷雪学、氷の先生です。ロシアのカムチャッカ半島の氷河をボーリングし、氷の中に含まれる物質を調べると、そのあたりに何千年前にどんな物質が空気中に漂っていたかがわかるのだそうです。
例えば、植物の花粉、窒素、黄砂、火山灰、放射性物質などです。なんと、アジア大陸のゴビ砂漠から飛んでくる黄砂の中に鉄分がかなり含まれていることを発見したのです。
アメリカのアラスカ大学で研究している間、共同研究者のカール・ベンソンさんから、空気中に含まれるダスト(粒子)の量と、サケや青魚(イワシ、サンマ、サバなど)の漁獲量が関係あるようだと知らされたのです。それまで、氷の研究者が魚のことを考えたことは、一度もなかったそうです。