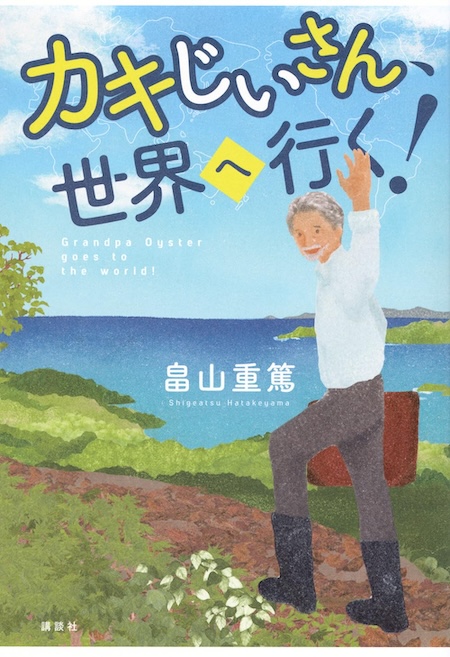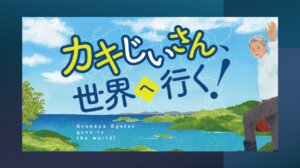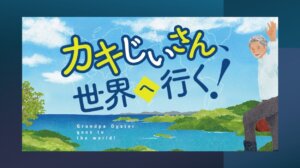カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。
そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く!』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。
「カキをもっと知りたい!」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。
これからあなたをカキの世界へ誘おう。連載23回の「北海道大学が発見した新事実…!「身体に毒」と思われた黄砂が、じつは「魚の養分」になっている驚きの理由」にひきつづき、今回も親潮に乗って北三陸沖にやってくるロシアの流氷の出発点を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。
【前編まで】
三陸沖の魚が豊かな理由は、意外なことに遠くアジア大陸からやってくる黄砂にありました。北海道大学の白岩孝行先生の研究で、黄砂には鉄分などの栄養が含まれていて、それが海に届くとサケやイワシなどの魚がよく育つことがわかったのです。石川県・能登半島のノリ養殖でも、黄砂が飛ぶ年はノリの色や成長がよくなることが昔から知られていました。自然と海の不思議なつながりが、ここにもあったのです。
黄砂の鉄分で青魚の漁獲量が増える
白岩先生もカムチャッカ半島の氷河の中に含まれる黄砂の量と、北の海の青魚(イワシ、サンマ、サバなど)の漁獲量の関係に気づき、研究を始めました。そして、年代別の黄砂の量と青魚の漁獲量のグラフを重ねると、ほとんど同じ曲線を描くことを発見するのです。黄砂に含まれる鉄分が、海の生産量に大きく関わっている。思ってもみなかったことでした。
白岩先生は、早稲田大学教育学部卒業です。子どものころは世界地図を広げ、ニコニコしている少年でした。その後、北海道大学大学院環境科学研究科で学び、雪や氷が好きになったそうです。1993年から2年間、第35次南極地域観測隊にも参加しました。
「地理学者の出番がきた」
白岩先生は、そう思ったそうです。世界地図をニコニコ見ていた少年は、地球を見下ろす目をもった地理学者になっていたのですから。
海の生物と鉄分の研究をしている第一人者が同じ大学にいたことも、幸いでした。海洋化学の松永勝彦先生です。松永先生を訪ね、鉄分と生物について、そして、気仙沼湾と湾にそそぐ大川の関係を学んだのでした。地理学者の目は、ロシアと中国の国境を流れるアムール川に向かっていきます。