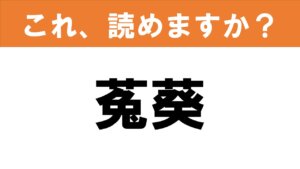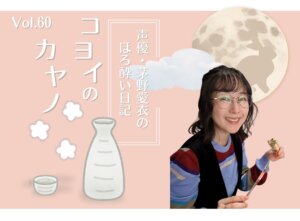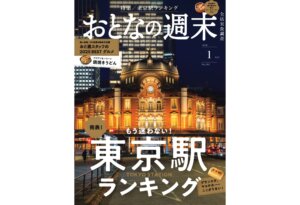言葉が先行している観のある『腸活』について、専門家にガイドラインを引いてもらう企画の後編。『腸活』の研究はどのように始まり、どこへ向かうのか。我々は日常において『腸活』をどう捉え、どう向き合えばいいのだろうか。【全2回・後編】
われわれは日常において『腸活』をどのように行えばいいのか?
京都府立医科大学・大学院医学研究科・生体免疫栄養学講座、内藤裕二教授をお迎えしての後編。『腸活』のスペシャリストに、『腸活』のこれまでとこれからを、詳しく訊いてみた。
──いわゆるウェルビー・フードも一般に浸透し、『Cycle.me』などはコンビニエンスストアでも販売されています。身近になったこれらの商品は、どのように実生活に役立てるのがいいのでしょうか?
内藤裕二教授(以下内藤)/食事と健康との関連は、今も昔も変わらず注目度が高いです。最近では機能性表示食品のように、食品の機能を手軽に知ることができる製品も、よく目にするようになりました。
腸活に関しては、腸内環境の改善や便通の改善は勿論のこと、近年では免疫や睡眠に関する注目度も高まっているように思います。
食物繊維は豆や根菜、海藻など食事から上手に取れれば理想的ですが、忙しい日々ではそれも難しいかと思います。食事に完璧を期すのが難しいのであれば、グア―豆食物繊維を含む食品をはじめとする“ウェルビー・フード”を、上手に活用していくのがよいのではないでしょうか。
──食物繊維にも種類があることを前回教えていただきました。われわれ一般人の生活においても、こうした種類の違いを意識したほうがいいのでしょうか?
内藤/ 食物繊維の種類まで気を遣っている人はまだそれほど多くないかもしれません。
しかしながら、先述の通り食物繊維の種類によって発酵性や発酵スピードなど、腸内細菌による利用のされ方や物理的な性質(粘度や水溶性など)に違いがあることが明らかとなっています。
そのため、近年では食物繊維によって期待できる生理効果の種類や強弱が異なるのではないかという考え方が一般的になってきています。私たち個人の腸内細菌にも個人差があることは広く知られており、個人ごとに自分の腸内細菌たちによって利用しやすい食物繊維が異なっているのかもしれません。
いろいろな食物繊維を比較検討される際は、ぜひ種類ごとの特徴を調べてみるようにしてみてください。