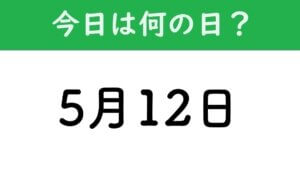バブル経済崩壊、阪神・淡路大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件など、激動の時代だった1990年代。そんな時代を、浅田次郎さんがあくまで庶民の目、ローアングルからの視点で切り取ったエッセイ「勇気凛凛ルリの色」は、約30年の時を経てもまったく古びていない。今でもおおいに笑い怒り哀しみ泣くことができる。また、読めば、あの頃と何が変わり変わっていないのか明確に浮かび上がってくる。この平成の名エッセイのベストセレクションをお送りする連載の第61回。作家と幼少の頃から交流があった母方のいとこがいた。生涯、凜凜たる勇気を持ち続けたその男は、作家の心に何を残したか。
愚直なまでにやさしかった1歳年長のいとこ
母方には大勢のいとこがいる。
本家は古い神社の神官を代々つとめており、学校が休みに入れば、東京の山の手や多摩地域に住むいとこたちは、示し合わせたように集まったものであった。
ローカル線とボンネットバスを乗り継ぎ、ケーブルカーに乗り、さらに30分も山道を登る。そんな山奥に、宿坊を営む広大な屋敷があった。
私たちにとって「山に行く」というのは、母の実家を訪ねることであり、同世代のいとこたちと林間学校のような生活を送る、年に何度かの行事であった。幼いころの思い出の過半は、その楽しい日々に埋めつくされている。
冬休みの午後であったと記憶する。
十数人も集まった同じ年ごろのいとこたちは、伯父から10円ずつの小遣いを貰って山歩きに出かけた。
そして当時大流行の「少年探偵団」を編成して、1日を楽しく遊んだ。
ぼ、ぼ、ぼくらは少年探偵団
勇気凜凜ルリの色──
まさかその30数年後に、わが連載エッセイのタイトルになるなどとはゆめ思わず、私も一団の末尾を唄いながら歩いたものだ。
門前のみやげ物屋で、それぞれがアメ玉やチューインガムを買った。伯父から貰った10円玉は、今日の100円ぐらいに相当したであろうか。ともかくけっこうな小遣いであった。
ところが、いざ買物をしようとすると、私の10円玉が見当らない。どうやら山歩きの最中に、どこかで落としてしまったらしかった。探しに戻ろうにも深い山道である。私は石段の中途に膝を抱えて泣いた。いとこたちはみなアメ玉をなめながら屋敷に帰ってしまった。
ただひとり、ひとつ年長のいとこが泣きくれる私を励ましながら、見つかるはずもない10円玉をけんめいに探してくれていた。
いとこの名はヒロシといった。きかん坊ばかりのいとこたちの中で、彼だけは温厚で物静かな子供だった。その性格はたぶん、物心つかぬうちに父親──すなわち私の母の兄と死に別れていたせいかもしれない。おしなべて幸福な家庭に育った他のいとこたちに較べ、彼だけはまちがいなく、苦労の分だけ大人びていた。
私は日ごろから泣かぬ子供だった。その私が膝を抱えて泣いたのはたぶん、10円玉を落としたからではないと思う。夕闇の迫る神社の、はるかな石段を行きつ戻りつして私の10円玉を探してくれているヒロシの、愚直なまでのやさしさに泣かされたのであろう。
山奥の冬の陽は、つるべ落としに昏(く)れてしまった。
「あったよ! ジロウ、あった、あった」
ヒロシはそう言って、私に10円玉を握らせた。とたんに私は、ヒロシのやさしい笑顔を正視できずに、声を上げて泣いた。子供心にも、その10円玉の出所がわかったからである。それはヒロシのポケットの中の10円玉にちがいなかった。
ヒロシは拒否する言葉も思いつかぬ私をみやげ物屋まで連れて行き、私の欲しそうなものを買った。
「ほら、食べろよ。もう泣くなって」
「ヒロシちゃんは?」
「おれは食べたくない。もうすぐごはんだから」
木下闇(こしたやみ)の帰り道で、ヒロシは泣きやまぬ私の手をずっと握っていてくれた。私が小学校1年、ヒロシは2年生だったろうか。ヒロシはそんな少年だった。
この原稿を、私はヒロシの生家に近い西新宿のホテルで書いている。足元にちりばめられた大都会の灯の中に、きょうばかりはあかりの消えぬ窓がある。