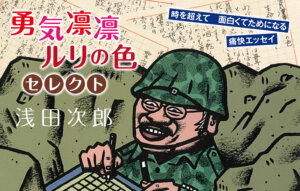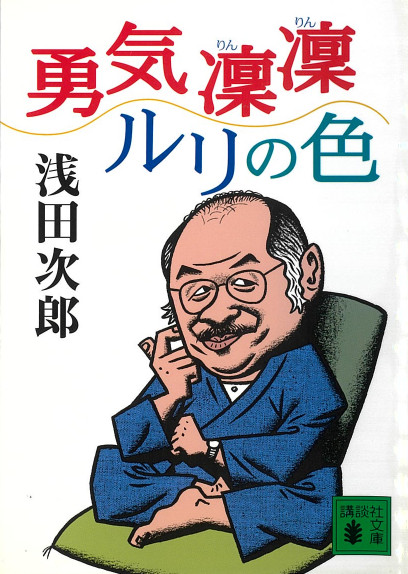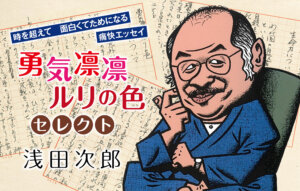新人自衛隊員たちの阿鼻叫喚の図
当時、新隊員の多くは農村出身者で占められていたから、教育の第一課目はとりも直さず「洋式便座の使用法」であった。十数名の班員は班長に引率されて隊舎の端にある広大なトイレに向かった。
ドアを開けたとたん、おおっとどよめきが起こった。
「注目! いいか、これが洋式トイレだ。使い方を知っとる者いるか」
愕くべきことに、挙手したのは私一人であった。実演して見せてやれというので、進み出て後ろ向きに座ると、その格好がよほど意外であったのか再びおおっとどよめきが起こった。ドアの外に鈴成りになって、隊員たちは目をみはっていた。
当時の自衛隊はものすごくマイノリティの職場であったから、何をするにつけても隊員たちの程度に合わせて、いちいち懇切丁寧な説明が加えられたものである。たとえば、
「えー、外人はクソと小便が同時に出ないから、便器もこういう形をしておる。したがってその点によく着目し、あらかじめ小便を済ませてからクソをするとよい」
とか、
「いつまでたっても要領をわきまえず、前向きの姿勢でクソをする隊員がおるが、何事も基本動作を正しく身につけねば上達はない。慣れぬうちはりきみも利かぬと思うが、くれぐれも前向きに座ったり、また便座に土足でしゃがんだりせぬように」
ドアに鍵がついていない、と誰かが質問をした。
「ウム。よい質問だ。自衛隊には任務遂行上に不必要なものはない。鍵がかからんと気が散って出るものも出んというやつは、こうしてドアの把手を内側から握っていればよい」
というわけで、その日から新隊員たちの洋式便座との格闘が始まった。
現実は思いのほか悲惨であった。たとえば、自衛隊にはすべてのドアをノックするという習慣がない。幹部室や事務室に入るときも、ドアの外で「○○二士、××班長に用事があって参りました、入ります!」と叫んでやおらドアを開ける。こういう躾(しつ)けは徹底される。
当然、トイレの作法もこれに準ずる。
生活に馴致(じゅんち)してくると、使用中のトイレをいきなり開けてしまっても、「やあ、すまん」「おお」で終わる。相手が上官であれば、「失礼しました!」「よおし」である。それが日常であるから、べつだんどうということもない。
ところが、まだ文化の落差にとまどっている新隊員たちにとって、これは重大事なのである。班長の説明にも拘(かかわ)らず、半数ぐらいの者はどうしてもズボンとパンツを完全脱却して前向きに座っている。躾け通りにノックをせず、いきなりドアを開けてそうした戦友のあられもない姿を目撃すると、ものすごくすまないという気がする。
「あっ、す、すまん……」「い、いや……」である。
毎朝同じことが繰り返される。自分も見られてしまうのと同時に、また他人の姿も目撃してしまうので、それがどれほどみじめな格好であるかは知っている。
そこでやむなく、「後ろ向きに土足で便座の上にしゃがむ」という、悲しい和洋折衷の体勢をみなが思いつくわけだ。これなら姿勢は不安定であるが、装具の完全脱却はしなくてもよいし、とりあえずドアの把手も確保できる。しかしまずいことには、入隊当初の精神的ストレスと慣れぬ食い物のために、みな下痢をしている。事は緊急を要するので、たいていはトイレに駆けこみ、力まかせにドアを引いてしまう。
当然の結果として、和洋折衷姿勢の戦友はひとたまりもなく確保したドアとともに転がり出てしまうのである。
ごくたまに、体が柔らかくて器用なやつが、初志貫徹の前向き姿勢のまま半身をねじ曲げて把手を握っていたりする。この場合はあおのけにどうと倒れる。しかも下半身は完全脱却されている。
「わわっ、大丈夫か!」「クソ!」である。
かくかくしかじか、私たちは四半世紀前の文化と安保の断層で、まこと笑うに笑えぬ労苦をなめさせられたのであった。
やがてそれぞれが便器の正しい使用法を修得し、「やあ、すまん」「おお」と、こともなげに言いかわせるようになったころ、私たちは敬礼の格好もさまになるいっぱしの兵隊になった。
自衛隊で俗にいうところの「シャバッ気が抜ける」とは、こういうことなのである。
今さら家族に自らの悲しい体験を語り聞かせて、洋式便座を悔い改めさせるほどの元気はない。
不本意ながら、これよりクソをする。
(初出/週刊現代1995年3月18日号)
浅田次郎
1951年東京生まれ。1995年『地下鉄(メトロ)に乗って』で第16回吉川英治文学新人賞を受賞。以降、『鉄道員(ぽっぽや)』で1997年に第117回直木賞、2000年『壬生義士伝』で第13回柴田錬三郎賞、2006年『お腹(はら)召しませ』で第1回中央公論文芸賞・第10回司馬遼太郎賞、2008年『中原の虹』で第42回吉川英治文学賞、2010年『終わらざる夏』で第64回毎日出版文化賞、2016年『帰郷』で第43回大佛次郎賞を受賞するなど数々の文学賞に輝く。また旺盛な執筆活動とその功績により、2015年に紫綬褒章を受章、2019年に第67回菊池寛賞を受賞している。他に『きんぴか』『プリズンホテル』『天切り松 闇がたり』『蒼穹の昴』のシリーズや『日輪の遺産』『憑神』『赤猫異聞』『一路』『神坐す山の物語』『ブラック オア ホワイト』『わが心のジェニファー』『おもかげ』『長く高い壁 The Great Wall』『大名倒産』『流人道中記』『兵諌』『母の待つ里』など多数の著書がある。