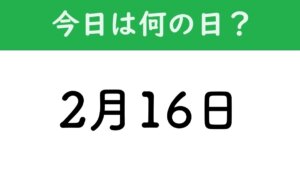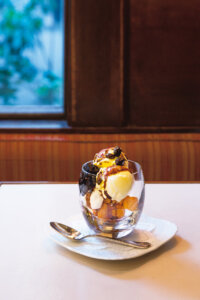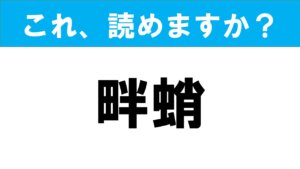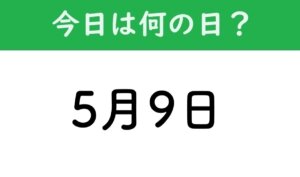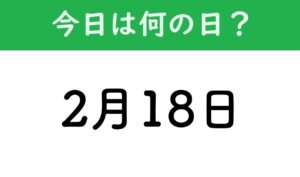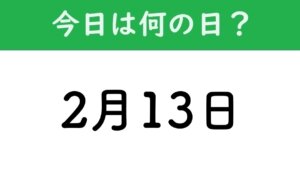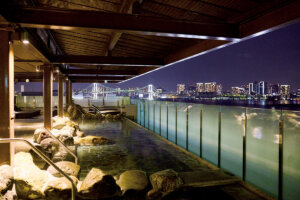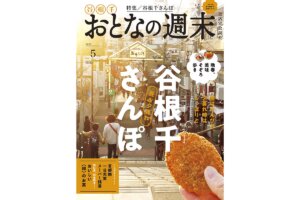「2月16日」。今日は何の日でしょう?答えは「天気図の日」!
新橋と横浜の掲示板に貼り出された天気図
1883(明治16)年2月16日、日本で初めて天気図がつくられました。ドイツの気象学者エルウェン・クニッピング氏(Erwin Knipping/1844~1922年)の指導のもと、日本全国11箇所ある測候所のデータを、江戸城本丸跡(現在の皇居東御苑周辺)に設置された東京気象台にて集計。クニッピング氏により、集計したデータから天気概況が英語で下書きされ、それを翻訳して日本語表記の天気図が作成されたそうです。
同年3月1日以降は1日1回発行、8月23日以降は、東京・新橋と神奈川・横浜の2箇所の掲示板で発表されました。天気図が専門的な知識がないとわからないことと、発表される地域が限定されていたため、当時はなかなか一般には認識されなかったようです。
そもそも天気図とは?
天気図(weather map)とは、広い地域で同時刻に観測された気圧・気温・風向・風力・天気などを天気記号で記入し、さらに等圧線・前線などを書き込んだ地図のことで、天気予報の基本となるもの。あの線と記号だけで天気を読んでいくのは、知識もさることながら豊富な経験がものをいいそう。「お天気占い」という言葉があるけれど、まさにそれ。当たるも八卦、当たらぬも八卦。でも最近の天気予報、何時に雨が降り出して、雨雲はこういう軌道で移動するといった細かい情報まで配信されていますが、これがまた結構バチコンビシッと当たったりするので驚きです。いったいどんな仕組みなのでしょうか?