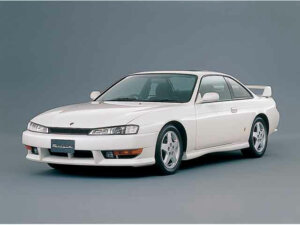複雑でわかりにくい「当分の間税率」。名称そのものが不可解!
そして、ガソリンはお米と同様、生活必需品になる。公共交通網が整備されていない地域では、クルマがなければ、通勤や日常的な買い物、通院などができない。クルマは生活を支えるインフラで、それを維持するのがガソリンだ。
補助金を支払う以前には、トリガー条項が考えられた。ガソリンに課せられた税金のうち、「当分の間税率」(=以前の暫定税率)を差し引くものだ。ただし東日本大震災の時、復興財源の確保が困難になるという理由で、トリガー条項は凍結された。そのまま今に至っている。
そもそも「当分の間税率」など複雑でわかりにくい。この背景には、ガソリン税の成り立ちが関係している。
なんでなの!? クルマの税金が一般財源(普通税金)に使われる
ガソリン税は、最初は道路建設に充てるための道路特定財源として、第二次世界大戦直後から高度経済性長期にかけて創設された。道路の建設や整備に必要な財源は、道路を損傷させる自動車ユーザーから徴収すべき、という考え方に基づいていた。
その後、ガソリン税の徴収を続けていくうちに、税額の不足が指摘された。そこで増税の手段として使ったのが暫定税率、つまり暫定的に引き上げられた税率だ。暫定的だから本来なら継続するものではないが、税収確保のために、暫定税率が継続的に適用されてきたのである。
問題はこの後で、2009年に道路特定財源制度が廃止された。ガソリン税、自動車重量税、以前の自動車取得税などは、すべて道路建設に充てるための道路特定財源として創設されている。
この制度が廃止されると、ガソリン税や自動車重量税は課税する法的な根拠を失う。それなのに依然として、一般財源(普通の税金)として徴収が続いている。つまり自動車を所有していると「普通の税金を多額に徴収される」ということだ。
そして、道路特定財源制度が廃止されたから、暫定税率の考え方もなくなり、「当分の間税率」という屁理屈のような名称変更を行って適用している。