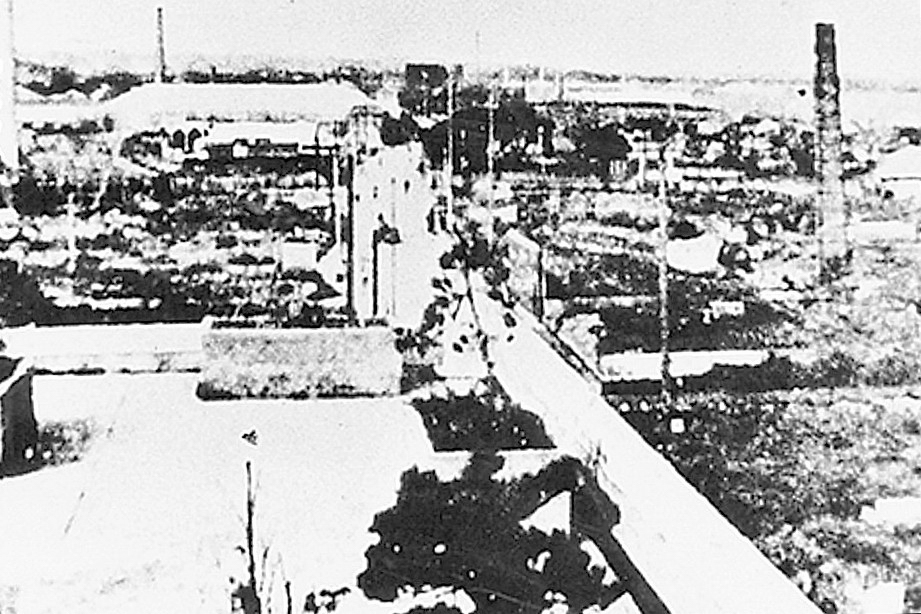廃止された鉄道の再起
売却が失敗に終わった旧線路敷は、会社清算人管理のまま、旧銚子遊覧鉄道と同一資本だった旅館「暁鶏館」の自動車部が、自社の旅客送迎用バスの専用道路として使用することになった。
このバス運行によって得た利益で、株式償還に必要な不足を補おうという腹積もりだったようだが、そもそもバス運賃が高価だったこともあり、利用客は伸び悩んだ。結果、バスの運行は長続きしなかったという。
銚子遊覧鉄道を設立した地元有力者らは、別資本の後ろ盾を得て、1922(大正11)年6月に新たに「銚子鉄道」という別会社を設立し、銚子遊覧鉄道と同じ区間の敷設免許を取得した。銚子における”鉄道事業”の再起である。この翌月となる7月には、件の旧線路用地(事実上の廃線跡)を旧・銚子遊覧鉄道の清算人から購入し、1923(大正12)年2月から線路敷設等の工事に着手した。同じ年の6月には、銚子遊覧鉄道の時代に計画されていた犬吠駅よりも先となる「外川駅」まで路線を延伸する認可を受け、その工事にも着手した。
こうして、「銚子鉄道」の設立からわずか1年足らずとなる1923(大正12)年7月5日、銚子駅~外川駅間の6.4kmを開通させた。銚子遊覧鉄道も同年11月26日付で“清算結了”となった。1925(大正14)年4月には、蒸気機関車や“ガソリン機関車”に代わる電車運転のための(電化)工事にも着手した。その3か月後の7月からは、「電車」による運行を開始した。
”銚子空襲”による廃線危機
先の大戦中の1945(昭和20)年7月には、電車に電力を送電する仲ノ町変電所が「銚子空襲」で焼失したほか、車庫や車両も戦災を受けた。このため「路線を廃止」することも議論され、それだけ空襲による被害は甚大なものだった。それでも、戦災を免れたガソリン機関車や国鉄(当時は鉄道省)から借り入れた蒸気機関車などを使用して12月には運転を再開させた。その後の1947(昭和22)年6月には変電所を復旧させ、電車運転も再開した。
1948(昭和23)年になると、戦時下の損失を整理するため企業再建整備法の適用を受け、そのための新会社として「銚子電気鉄道」を発足させ、これが現在に至る銚子電気鉄道のはじまりであった。なお、銚子鉄道は「特別経理会社」として戦時下の損失などの事後処理に専念する会社となり、その使命を終えると解散した。