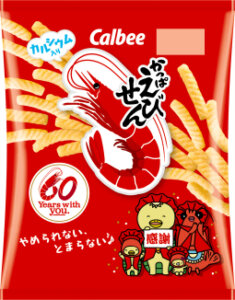日本特有の四季の「風物詩」
日本では春夏秋冬の四季があり、昔から日本人は季節に合わせた「風物詩」をさまざまな形で楽しんできました。
例えば食べ物。「旬のものを食すると健康に過ごすことができる」として、夏には身体を冷やす食べ物を、冬には身体を温める食べ物を食するなど、風習や知恵とともに生活に根付いてきました。
立秋の頃に旬を迎える食材は「桃」「無花果(イチジク)」「なす」「ズッキーニ」などです。確かにこの季節にいただく「桃」は瑞々しくておいしいですね。
また古くから日本人は、日本の美しい四季を「俳句」に詠んで楽しんできました。正岡子規の『秋立つやほろりと落ちし蝉の殻(立秋だなぁ。ほろりと木からセミの抜け殻が落ちていったよ)』や、高浜虚子の『怪談はゆうべでしまひ秋の立つ(怪談は夏の間に行うものだから昨夜でおしまい。今日は立秋の日だ)』は「秋立つ」という季語を使った「立秋」の句です。
ちなみに「暑中見舞い」は立秋を境に「残暑見舞い」に切り替わりますのでご注意を!
立秋以降秋に向かって、セミをはじめたくさんの虫が鳴き始めます。実は虫の鳴く声を「虫の声」や「虫の歌」と認識して楽しむ感覚を持っているのは日本人だけで、欧米人にはただのうるさい雑音にしか聞こえないんだそう。
ということで、今年はぜひ立秋を意識して、日本人としての情緒を粋に楽しんでみてはいかがでしょうか?