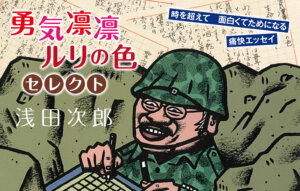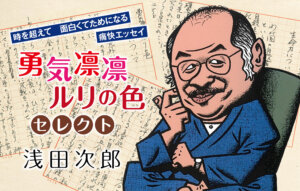バブル経済崩壊、阪神・淡路大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件など、激動の時代だった1990年代。そんな時代を、浅田次郎さんがあくまで庶民の目、ローアングルから切り取ったエッセイ「勇気凛凛ルリの色」は、30年近い時を経てもまったく古びていない。今でもおおいに笑い怒り哀しみ泣くことができる。また、読めば、あの頃と何が変わり、変わっていないのか明確に浮かび上がってくる。
この平成の名エッセイのベストセレクションをお送りする連載の第108回は、「員数(いんずう)について」。
旧軍、及び自衛隊で用いられる特殊用語
タイトルの意味を知っている人は少いであろう。
「員数」は、旧軍経験者、現職自衛官もしくは出身者だけが理解しうる特殊な言葉で、純粋な軍隊用語と言ってよい。私はかつて自衛官であったので、これを知っている。
ということは、一般社会ではほとんど死語同然なのであるが、極めて便利な意味深長な平明な合理的な傑作造語であるので、ここに紹介しておく。「員数」はたとえば部下を責めるによく、上司をなじるによく、同僚の陰口にもよく、そのほか家庭においても多用できる言葉である。この項を読んだその日から、読者もしばしば使うであろうことうけあいである。
手元の辞書によれば「員数」とは「物の個数。特に、ある箇所で定められた一定の個数」である。しかし、軍隊社会ではこれを拡大的に解釈し、一個人の習慣、性格、行動、道徳の指標として日常的に使用する。
そもそも軍隊等(以後旧軍及び自衛隊をこう呼称する)において、ヒトとモノは余り区別がないので、「員数」は「定数」もしくは「定員」のことである。もちろん一種の生活用語であり、公式には使われない。
「第一小隊の員数は30名だ」とか、「第一営内班の煙缶(えんかん・灰皿)の員数は3個、ホウキは3本、雑巾は6枚」などというふうに使用される。
「員数が合わない」というのは、「定員もしくは定数が足りない」ということで、軍隊等ではもちろん大問題である。そのためにしばしば「員数合わせ」が行われる。
たとえば演習に先だち小隊員の員数が足らんので、糧食班に臨時勤務に出ている兵隊を呼び戻し、員数を合わせる。
補給品の点検に際して下着が1枚足らんので、とりあえず売店(PX)で官品に似た形のシャツを買い、員数を合わせる。
さらに、「員数をつける」という言葉がある。これは「強引に員数を合わせる」というほどの意味である。対象がモノである場合、「盗む」の同義語となる。
たとえば補給点検に際して、員数合わせのコツを知らない新兵と、鬼より怖い補給陸曹(下士官)の間に、よくこんな会話がかわされる。
「半長靴(はんちょうか)が1足しかないぞ。どうした」
「はい。朝にはあったのですが、員数をつけられました」
「バカヤロー、点検の前にはよく掌握しておけ。員数つけられたら、員数つけてこい」
と、このように「盗まれたら盗み返せ」という論理が、軍隊等では罷(まか)り通るのである。
「員数を掌握する」はひとつの成語で、「定数を確保する」という意味である。軍隊等におけるヒトまたはモノは、すべて広義での武器であり、国家の所有にかかる「官品」であるから、「員数の掌握」は軍人等にとって最優先のモラルということになる。
そこで、「たとえ盗んででも員数は掌握しておく」という論理が成立する。
元来、軍隊等は塀の内外を自由に往還することのできぬ閉鎖社会である。すなわち、ヒトが失踪したり、モノを紛失したりすることは、物理的にいって有りえない。ヒトがいなくなったのは「逃げた」のであり、モノがなくなったのは「盗まれた」のである。
盗まれたにはちがいないのであるが、そう言うのは余りに不穏であるし、またそう言うのとは道徳上ちとニュアンスがちがうので、「員数をつけられた」と称する。
今の自衛隊は物資も豊かであろうから、員数についてはさほど神経質ではないかもしれない。しかし、私が在職した昭和40年代は旧軍出身者も多く残っており、かなり色濃く旧軍の伝統を踏襲していた。員数をつけたりつけられたりするのは日常茶飯事、というより、ほとんど営内生活の一環であった。
では、個人の幸福のためにやたら他人の物品を掌握してよいかといいうと、そうではない。犯罪ではなく生活の一環であるのだから、暗黙のルールがちゃんとある。員数をつけるときは他中隊から持ってくるのである。