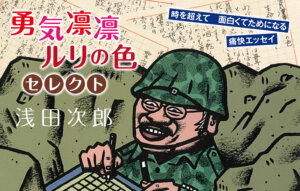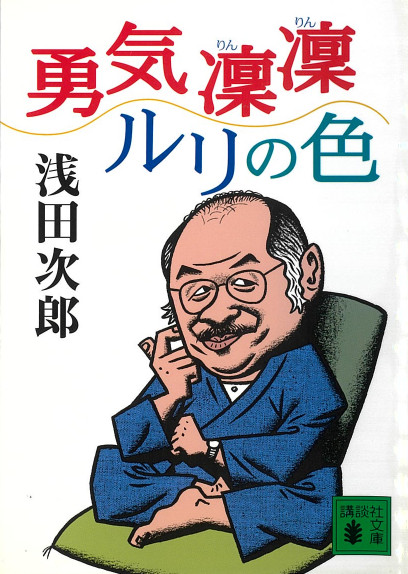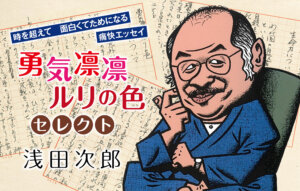「便座について」
バブル経済崩壊、阪神・淡路大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件など、激動の時代だった1990年代。そんな時代を、浅田次郎さんがあくまで庶民の目、ローアングルからの視点で切り取ったエッセイ「勇気凛凛ルリの色」は、30年近い時を経てもまったく古びていない。今でもおおいに笑い怒り哀しみ泣くことができる。また、読めば、あの頃と何が変わり、変わっていないのか明確に浮かび上がってくる。
この平成の名エッセイのベストセレクションをお送りする連載の第65回。現在60歳以上の世代が子供の頃、まだ住宅のトイレは和式の方が圧倒的に多かった。そんな彼らは西洋式の便座の初体験をどのように乗り越えてきたのか。
西洋式便座が異物だった時代があった
私は狂信的な国産品愛用者である。
いわゆる海外ブランド品には全く興味がなく、むしろ軽蔑し、憎悪している。昔から一貫して時計はセイコー、万年筆はパイロット、車は三菱、犬は柴犬、猫はミケ、と決めている。旅に出るときもJALかANA以外は信用せず、通じようが通じまいが徹頭徹尾、世界の涯はてまで日本語をしゃべり続ける。
趣味というよりも、むしろ信仰に近い。当然のことながら生活様式もすべて和風に統一し、書斎にあっては古色蒼然たる文士スタイルで座机に向かい、夜は蒲団を敷いて寝る。
したがって、生活の中に機能性と合理性を求める家人との間には常に諍(いさか)いが絶えない。つまり亭主の趣味に従っていると、家事労働が倍になる、というわけだ。
しかし家では私が法律なので、家族の請願は一顧だにされず、娘はかわいそうに和室でピアノを弾いている。
唯一の例外は便所である。私にとっての便所は決してトイレではなく「厠(かわや)」であるので、当然わが国固有の伝統と格式を誇る「きんかくし」を採用したのであるが、ある日旅から帰ると、無断で洋式便座に改良されていた。
私の失意と絶望は名状しがたいものであった。実はこの洋式便座こそ、私の最も軽蔑し、憎悪する代物なのである。趣味の問題ではない。理由はちゃんとある。
第一にりきみが利かぬ。第二に排便を観察できぬ。第三に便座に肌を接することは、不快かつ不衛生である。第四に姿勢が屈辱的である。
しかし喧々囂々(けんけんごうごう)たる家族会議の結果、一対三の多数決を以ていまわしき西洋便座は不動のものとなってしまった。私の正当な主張がナゼ理解されないのか、今もって腑に落ちない。
ところで、私が初めて西洋式便座なる異物を使用したのは小学生のころである。生家が没落する前のこととて、私は私立のミッション・スクールに通っていた。当然お友達はみな貴顕であった。ある日、初めて遊びに行った友人の家に、それがあったのである。
洋式便座どころかほとんどの家が汲取式であった昭和30年代のこと、ドアを開けたとたんの私の愕(おどろ)きととまどいは、まさに驚天動地のものであった。もっとも、同年輩以上の読者諸氏はみないちどは、この強烈なカルチャー・ショックを体験しているであろう。
で、みなさん同じことをしたと思うのだが、私もしごく自然に考えて、前向きにまたがった。その瞬間に正しい使用法──すなわちドアに向き合った後ろ向きの姿勢を考えついた方は、まずいないと思う。
そのとき私はハッキリとこう考えた。アメリカ人は何とマメなのだろう。いちいちパンツを床に脱ぎ置いてクソをするのか、と。
さて、時勢の赴(おもむ)くところその後あちこちに洋式便座は出現することになるのだが、多くの方がたぶんそうであったように、私もそれを使用するのはよほどの緊急の場合に限られていた。
どうしても使わざるを得なくなったのは、昭和46年の春、自衛隊に入隊したときである。朝霞駐屯地の教育隊隊舎は、つい先ごろまで米軍が使用していたために、すべての便器が洋式だったのである。