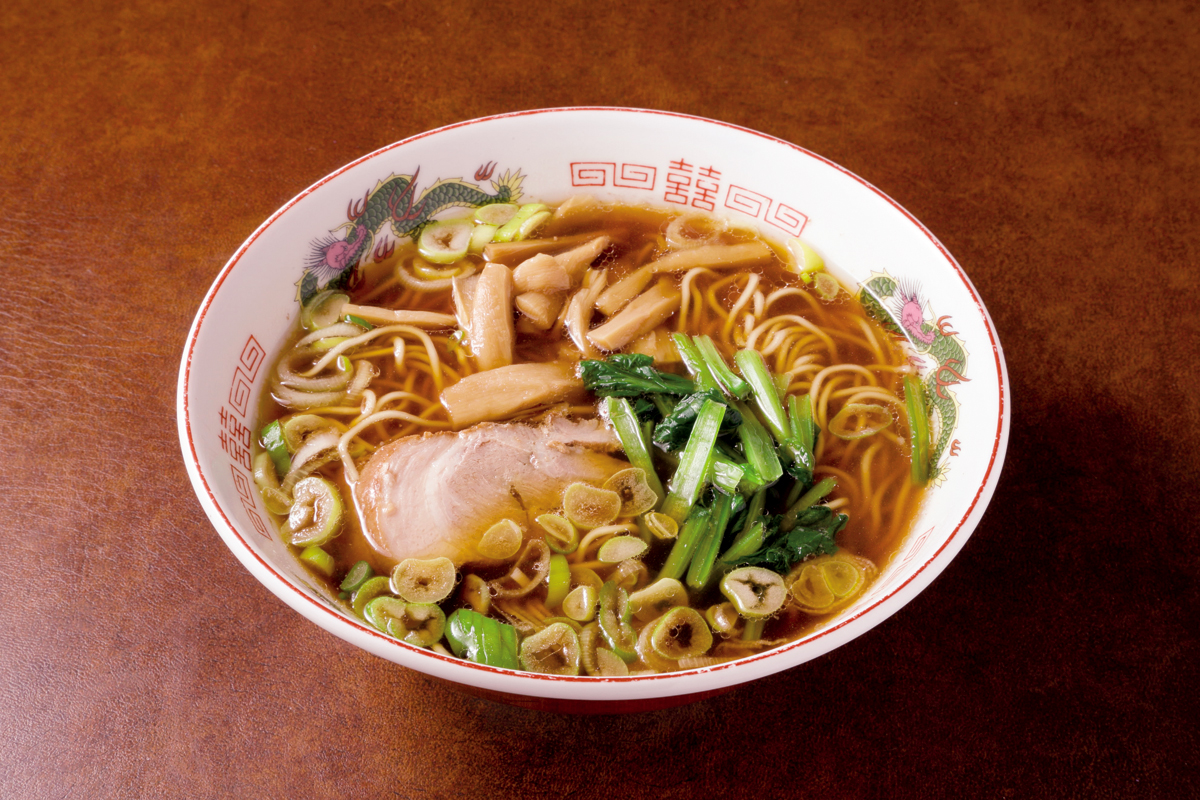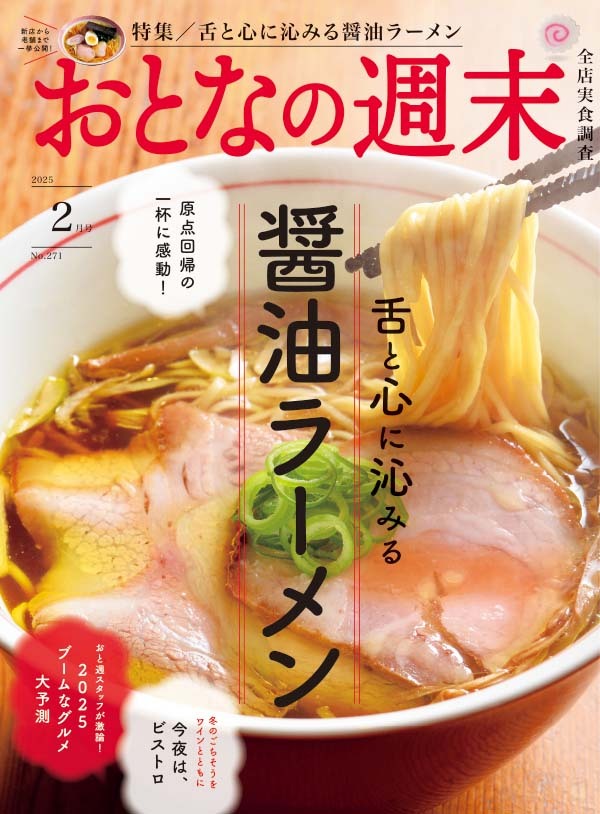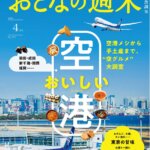ラーメンの歴史…つっても皆さん、ラーメンウンチクって聞き飽きてない?ベラベラ語るヤツ多いけど誰も聞いてねェよ。そんなウンチクとは一味違う外伝的な歴史をどうぞ!
歴史を振り返る!ラーメン史外伝
紀元前 8400頃:中央アジアにてラーメンの麺の原料となる小麦の栽培が始まる。
西暦 1488年:京都の相国寺で、臨済宗一山派の僧・亀泉集証が小麦粉をかん水で練った日本初の中華麺「経帯麺」を食べる。
1597年頃:ラーメンには欠かせない「醤油」という文字が初めて登場した文献・日常用語辞典『易林本節用集(えきりんぼんせつようしゅう)』が作られる。
水戸黄門がラーメンをふるまった!
1697年:徳川光圀が隠居所の西山荘でラーメンを客にふるまった。つい最近までこれが「日本初のラーメン」と言われていたが、1488年の亀泉集証の記録が2017年に発見され、黄門様は日本初の座を明け渡すこととなる(諸説あり)。
1851年:木綿の糸繰機にヒントを得て製麺機を発明し「佐賀の発明王」と呼ばれた真崎照郷が、現在の佐賀市巨勢町に生まれる。
1937年:後の「全国ラーメン党会長」林家木久扇(前名・初代林家木久蔵)が、東京都日本橋に生まれる。
1944年:後の「全国ラーメン党副会長兼大阪支部長」横山やすしが、高知県に生まれる。
1959年:料理のラーメンとはまったく関係ない、ドイツ語で「枠」を意味する「ラーメン(Rahmen)」から名付けられた建築構造「ラーメン構造」による日本屈指の名建築「国立西洋美術館」が竣工。蛇足ではありますが「ラーメン構造」の中には「山形ラーメン構造」という構造もあり、ラーメン処で知られる山形県と混同しやすく、ますます話はややこしくなっている。