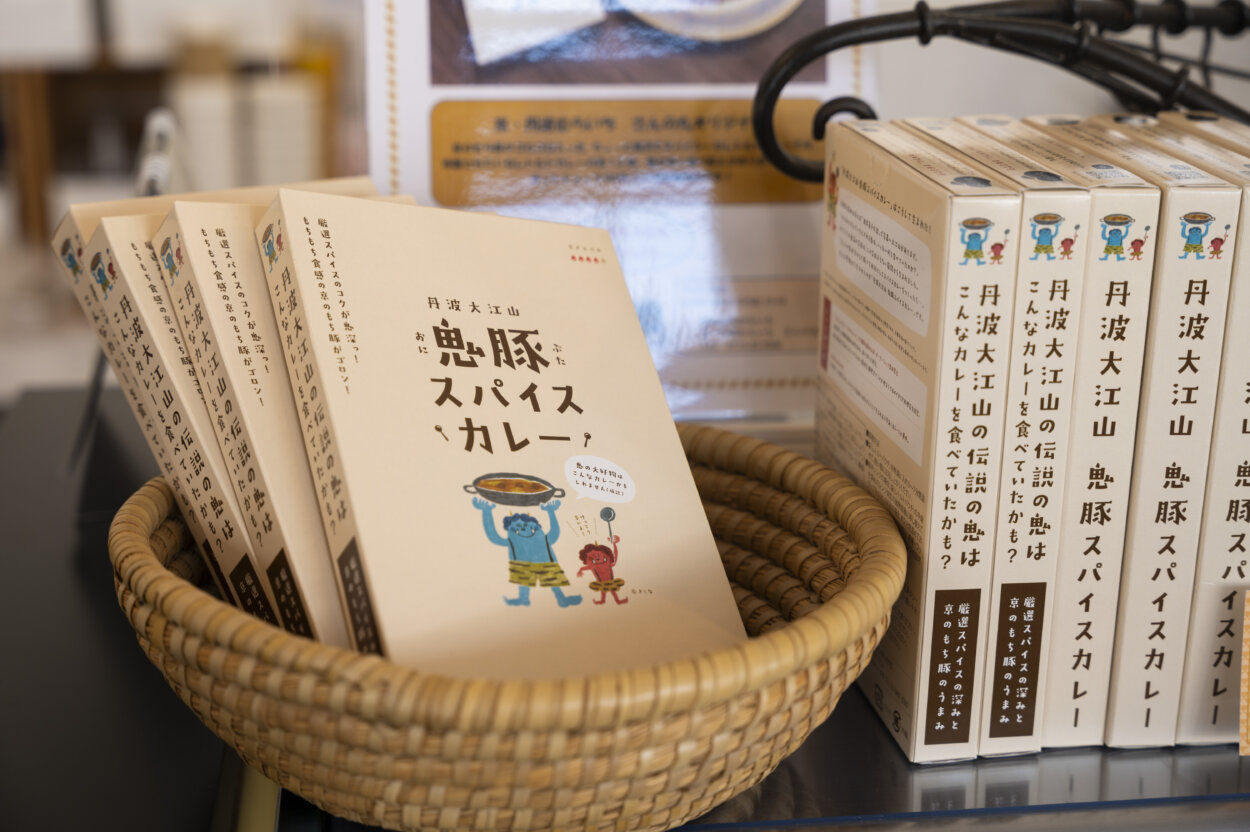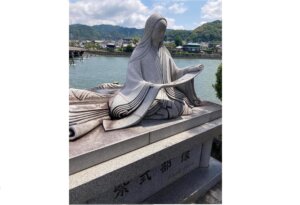京都丹波地方。長野県の小布施や愛媛県の中山と並び、栗の名産地として日本中に名を馳せる場所。そこで生まれるのが丹波くりだ。栗の旬といえば秋だけれど、日本人に古くより愛されてきた栗は、四季を通じて、その豊かな味わいを楽しませてくれる。パティスリーに行けばいつだってモンブランが食べられるし、スーパーマーケットには栗の甘露煮が並び、コンビニには普通に甘栗が売っているし、最中の栗入りはちょっと贅沢で。
歴史的にも京都は栗の名産地
国内外さまざまな品種があるのだけれど、丹波くりの存在は特別だ。平安時代から栗の栽培が行われていた丹波は、朝晩の気温の寒暖差が大きいうえに、日照条件がいい。この気候が栗には最適な環境をつくり、時代とともに改良も進んだことによって、品質は国内産の中でとびきり高い。
それと見た目。丹波くりの特徴となる大ぶりの姿は、大きいものになると男性の手でも3、4粒ほどしか乗らないほど。ちなみに丹波くりとは丹波で採れる高品質な大栗の総称であって品種名ではない。ブランド名といったところだ。
現代では主に〈銀寄(ぎんよせ)〉と〈筑波〉という品種なのだとか。ともに日本を代表する栗の品種で、全国の多くの場所でも栽培されている。〈銀寄〉は豊かな甘みが特徴で、「栗の王様」とも言うべき存在。〈筑波〉は栗の香りが強い優等生。その中でも丹波くりは別格ということ。
もうひとつ、丹波くりが特別な存在となる理由がある。それが歴史。西暦700年代の「日本書紀」や900年代の「延喜式」ですでに丹波くりを想起させる記載があるのだとか。
また、江戸時代には丹波の大名たちが丹波くりを朝廷や幕府へ献上しており、高貴な献上品として全国にまで知れ渡っていた。丹波地方で魚行商をする尼崎の商人たちが帰路の道中で丹波くりを売り歩き、参勤交代などで尼崎を通過する武士たちが江戸や郷里に持ち帰って広まったという話もある。歴史の中で、すでに丹波くりは上等なものであり、栗といえば丹波くりであったわけだ。