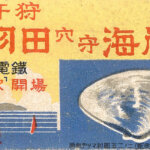念願の羽田空港ターミナルへの乗り入れ
1984(昭和59)年にはじまった「沖展(沖合展開事業)」と呼ばれた羽田空港の拡張工事。1993(平成5)年9月の“ビッグバード”と呼ばれた第1旅客ターミナルビルの開業に合わせるように、京急・空港線も同年4月1日に穴守稲荷駅~羽田駅(現在の天空橋駅)間の地下新線を開業させた。
この地下新線の工事に伴い、1991(平成3)年1月からは、穴守稲荷駅~旧・羽田空港駅間の運転を取り止め営業休止とし、空港線は蒲田駅~穴守稲荷駅での折り返し運転を行った。地下線区間が開業すると、羽田駅(現・天空橋駅)で”東京モノレール”へと接続したことで、空港ターミナルへのアクセスが可能となった。
その後、1997(平成9)年11月には空港線の中間駅である大鳥居駅が地下化され、翌1998(平成10)年11月18日に、羽田駅(現・天空橋駅)から羽田空港駅までが延伸開業すると、羽田駅は「天空橋駅」と改称された。2010(平成22)年になると、羽田空港国際線ターミナル駅(のちの羽田空港第3ターミナル駅)が開業し、それまでの羽田空港駅は「羽田空港国内線ターミナル駅(のちの羽田空港第1・第2ターミナル駅)」へと改称した。
地上線時代の廃線跡をたどる
以前の京急・空港線は、主要国道や都道との「平面交差(踏切)」が存在していた。具体的には、蒲田駅のそばには「お正月の箱根駅伝」でも有名だった国道15号線を横断する踏切と、大鳥居駅付近にも産業道路(都道6号線)と環状8号線(都道311号線)を横断する踏切があった。これらは「交通渋滞」のネックとなっていた。この踏切を解消するため、それまで地上を走っていた空港線(旧・穴守線)は“立体交差化”され、一部区間を除き”高架区間”または”地下区間”を走る線形へと姿を変えた。
現在の空港線は、京急蒲田駅、糀谷駅は高架区間に、大鳥居駅は地下区間となった。高架区間を除けば、線路が地下に潜った線路敷の多くは、駐車場や自転車駐輪場などに転換された。糀谷駅~大鳥居駅間には、「高架線から地下線」へと切り替わる区間があり、この区間は地上を走る線路がそのままだ。また同様に、穴守稲荷駅も地上線のままである。
「穴守稲荷駅だけが、なぜ地上駅のままなのか?」という疑問を耳にすることがある。これには「公共工事」が関係する。大鳥居駅は道路との“立体交差事業”として実施されたもので、いっぽうの羽田空港への地下線は“空港拡張工事”として施工されたものである。この二つの工事に挟まれた“穴守稲荷駅”は「これらの工事と関連しない」として、既存の線路に手をつけなかっただけに過ぎない。むしろ、昭和の風景を色濃く残す「踏切のある街並み」は、今のご時世にとっては“貴重な存在”となるだろう。
文・写真/工藤直通
くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。