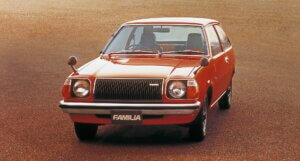ユーザーのニーズに合わせて改良
職場の先輩の証言でもいいところ、悪いところのあった初代テラノは1986年にデビューして、1995年まで販売された。これは日本の話で、実はこの初代モデル、2006年までインドネシアで生産されて東南アジア地域で販売されていた。そのため、インドネシアなどでは今も現役で走っている姿を目にする。
日本の話に戻そう。初代テラノは2ドアモデルのみで、エンジンは2.7LのOHVディーゼルを搭載して登場。その後クロカンブームの盛り上がりもあり、ユーザーのニーズに合わせて仕様を追加して販売増強に力を入れた。
エンジン改良、ボディ追加で魅力アップ
エンジンで言えば、ライバルに対して見劣りするということで、1987年にV6、3LのSOHCを追加してガソリンエンジンが欲しいというニーズに応え、1988年にディーゼルターボを追加してパワーアップのニーズに応えた。
一方、2ドアモデルが主流だったクロカンも人気が4ドアモデルに移行しつつあるのを認識した日産は1989年に4ドアモデルを追加。ただ4ドアモデルは、リアの三角窓がなく普通っぽいデザインになったのは残念。
そして、1993年のマイナーチェンジでは、大迫力のオーバーフェンダーを装着したワイドボディを追加するなど、あの手この手で改良していった。
RVブームでは苦戦を強いられた
改良により進化を続けた初代テラノ。1980年代中盤以降の第一次クロカンブームの主役に君臨し、日本のユーザーに新たな楽しみを提供してくれた。しかし、1991年にデビューした2代目三菱パジェロの登場により勃発したRVブームでは苦戦。
そのひとつは、クロカンのデザイントレンドが洗練より迫力重視になった点は否めない。立派なグリル、目立つ顔、存在感のある肉感的なリアなどに象徴されるデザイントレンドの前にテラノは苦戦を強いられた。
それから、1986年デビューで、しかもベースはさらに古いダットサンピックアップという点で並みいるライバルを相手に設計の古さが隠せなくなってしまった。
モデル末期では苦戦したが、チャレンジングなモデルで、しっかりとユーザーの心をつかんだ初代テラノの功績は評価すべきだろう。コスト計算もしっかりされていて、ユーザーのニーズに合わせて細かく改良&追加してきたその姿勢は今の日差にはない。
それが今後再建を目指す日産にとって、初代テラノのようなモデル、初代テラノで実践した姿勢が必要になってくるはずだ。
【日産テラノR3M主要諸元】(正式にはMは3の左上に入る)
全長4365×全幅1690×全高1680mm
ホイールベース:2650mm
車両重量:1700kg
エンジン:2663cc、直4OHVディーゼル
最高出力:85ps/4300rpm
最大トルク:18.0kgm/2200rpm
価格:233万3000円
【豆知識】
日産デザインインターナショナル(NDI)は1979年4月に設立された日産デザインのアメリカ拠点。前衛的なコンセプトカーをデザインする傍ら、1986に登場した初代テラノ、クーペボディとキャノピーボディをそれぞれ載せ替えできるエクサをデザインしたので有名。日本では載せ替えが認可されなかったのが残念。そのほかNXクーペ(1990~1994年)、レパードJフェリー(1992~1996年)などもデザインを担当。現在は日産デザインアメリカ(NDA)として、日産車のデザインを手掛けている。
市原信幸
1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師(旧ペンネームは池沢さとし)先生の漫画『サーキットの狼』(『週刊少年ジャンプ』に1975~1979年連載)に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社(現講談社ビーシー)に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。
写真/NISSAN、MITSUBISHI、PORSCHE