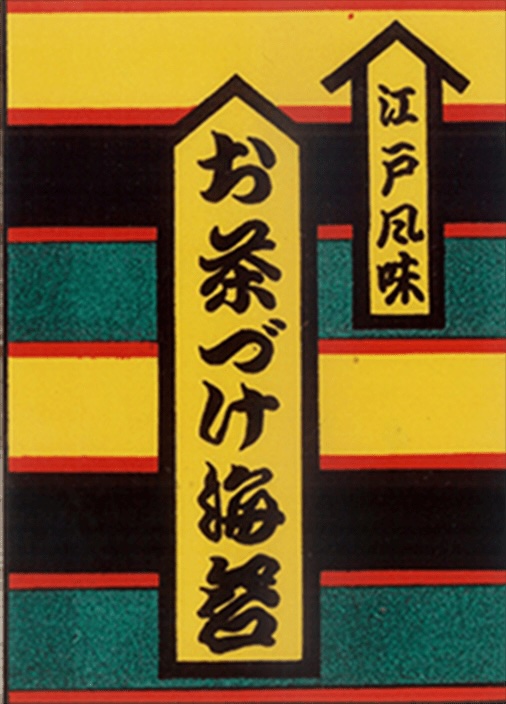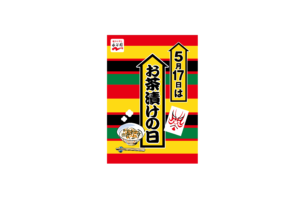「お茶づけ海苔」や「松茸の味 お吸い物」など、『永谷園』(本社:東京・西新橋)のロングセラー商品は、その商品名を聞いただけで味や香りはもちろん、パッケージ、CMが思い浮かぶという方は少なくないだろう。同社の商品が愛され続け、ロングセラーとなっている秘密を同社の広報部や開発部のメンバーから探った。
美味しい・簡便は当たり前! 永谷園流・ロングセラーの育て方
永谷園のロングセラー商品で、あなたの心に刻まれているものは何だろう。発売年順に見てみると、「お茶づけ海苔」(1952年発売〈以下同〉)、「松茸の味 お吸い物」(64年)、「あさげ」(74年)、「すし太郎」(77年)、「麻婆春雨」(81年)、「広東風かに玉」(85年)、「チャーハンの素」(87年)、「おとなのふりかけ」(89年)、「煮込みラーメン」(93年)となっている。
これらの共通点は、簡便であることと憧れを手の届く存在にしたこと。例えば「お茶づけ海苔」は永谷園本舗(現・永谷園ホールディングス)の創業者・永谷嘉男(1923~2005年)によって「小料理屋の〆で出るお茶づけが家でも食べられたら」という思いから生まれた創業商品。「すし太郎」は当時の子どもたちが食べたいメニューベスト3にお寿司が入っていたから、なのだそう。
商品企画、品質開発にも携わってきた広報部長の小川美朋さんは次のように話す。
「簡便であることはもちろん必要なのですが、それを支える品質がきちんとしていることが大前提です。それゆえ、原材料の吟味・品質チェックを徹底しています。特に『お茶づけ海苔』は発売以来70年超、味はほぼ変えていません。商品裏面の表示の通り、原材料は、抹茶・海苔・昆布と非常にシンプルなため、原料がそのまま味として反映される、ごまかしがきかない商品です」
昆布などは天産物ゆえ、収穫年や産地によって、当然ながら味や風味に違いが出てくる。それに近年の大きな気候変動により、それら原材料を取り巻く環境も変わっている。
「だからこそ、同じ味にするために調整します。塩分などの成分分析も当然行います。しかし、まったく同じ分析値なのに味が違ったり、色が異なったりということはあるので、どれほど機械化が進んでも実際に人が食べてチェックすることは必ず続けていきます」(小川さん)
永谷園広報部の淡路大介さんも、商品企画に携わってきた一人だ。「厳しい品質管理は、どのメーカーさんも行っておいでだと思います。ただ弊社のお茶づけは、変わらないことを貫いているからこそ、原料段階でも、 実際にお茶づけの形まで加工してからの品質チェックも複数回しています。元原料の部分から味や香り、色みなど、さまざまな軸の中で確認し、場合によってはそのロットごと弾くケースもあります」と話す。
天産物だからどうしても味にブレは出る。そのため味の上限と下限の基準範囲内が決められているが、永谷園の担当者が気づかないレベルでも、味が変わったと感じるほどのロイヤルユーザー(そのブランドを継続して買う客)もいるのだそう。例えば、あられの焼き色が少しブレただけでも、香ばしさが出過ぎて味が変わったと連絡が入る場合もあるのだとか。
それを聞いて、大ファンだからこそ、愛するが故、親切心で言ってくれるのだろうなぁと、世知辛いこの世の中において微笑ましく映った。