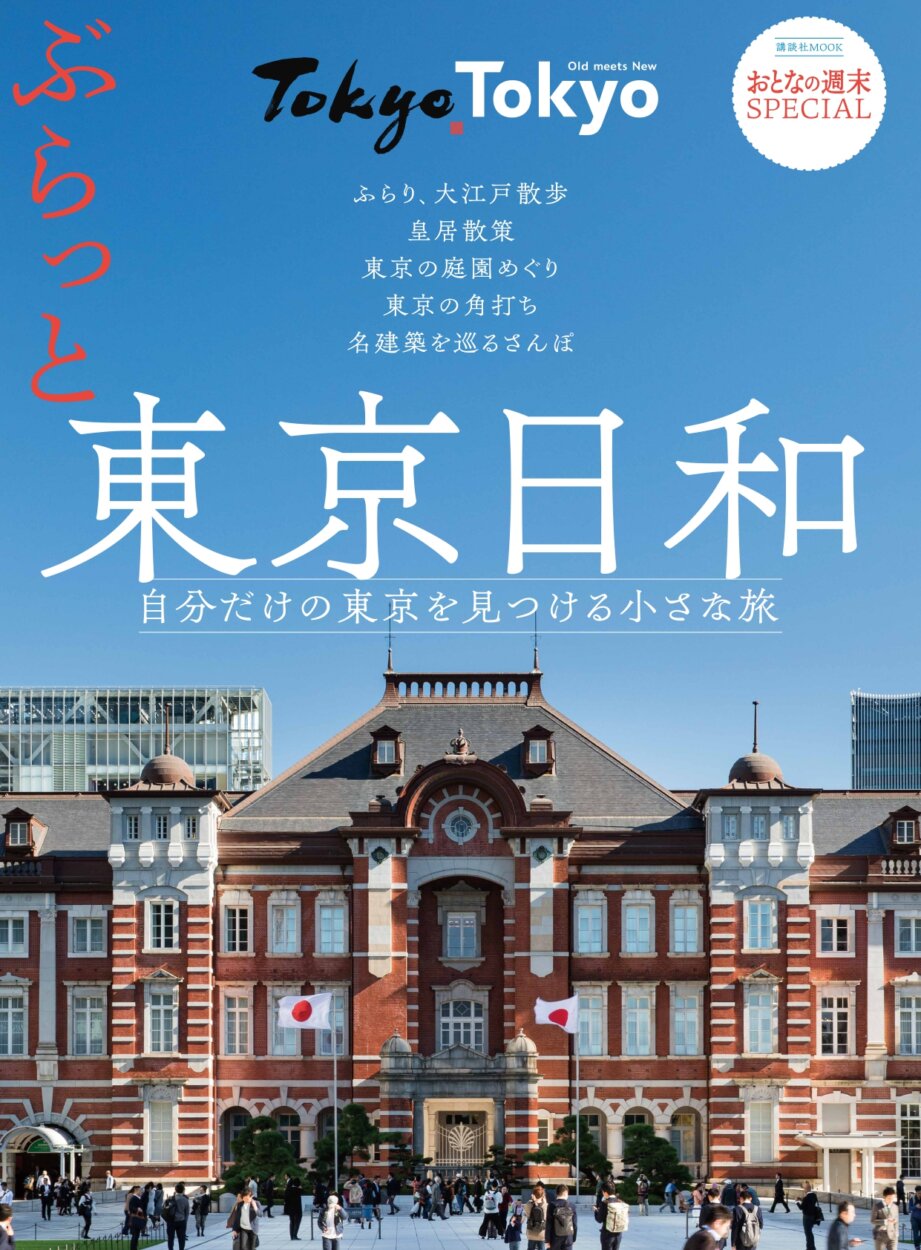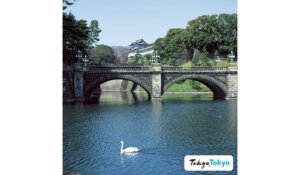東京にはいくつもの川が流れている。普段何気なく眺めている川も、川に沿って歩いてみると、史跡がいくつもあり、名も知らぬ花が咲きと、実に色々な表情を持っていることに気付く。週末の散策にぴったりな3名川を歩いてみました。今回はその中から映画や歌との縁のある神田川をご紹介します。
日本の都市上水道の歴史を探索できる川
フォークソングで泣け、水道事業に感銘する川、神田川である。ある年代以上の読者の皆様ならば、この名称を聞いて思い出すのは南こうせつとかぐや姫が歌った『神田川』だろう。景気のいい高度成長期。その側面にあった、どこか白けた若者たちの不安な心情を吐露した四畳半フォークの名曲である。ただ神田川には、そんなフォークソングのイメージがある一方で、日本が世界に誇る都市上水道の曙でもあったという歴史的事実もある。神田川とはもともと、江戸時代初期に、江戸城下に飲料水を供給するために作られた『神田上水』だったのだ。流れに沿ってそぞろ歩いてみれば、『神田川』で歌われた三畳一間の下宿や横丁の風呂屋はもはやほぼ見当たらないが、神田上水の足跡は至るところに残っているのだ。神田川を散策することは、これすなわち、日本の都市上水道の歴史を辿る旅といってもいいかもしれない。
徳川家康が命名”お茶の水”
その水源地である井の頭池を巡れば、徳川家康が、「関東一の名水!」と讃えお茶を淹れたという伝説から命名された湧水『お茶の水』を、今も見ることができる。現在は周辺開発などが原因で、その湧水量が減った為、ポンプで水を汲み上げているそうだが、まさしくここが神田川のはじまりのはじまり!
神田川と言えばの 『神田上水取水口大洗堰跡』
そして神田川を語るうえで忘れてはならない場所がある。地下鉄有楽町線の江戸川橋駅近くの江戸川公園内にある『神田上水取水口大洗堰跡』である。寛永6年(1629年)頃に完成したといわれる神田上水だが、江戸湾の海水は満潮時にはこの辺りまで入ってくるため、ここに“大洗堰(おおあらいせき)”と呼ばれる堰を作って海水の遡上を停め、そのすぐ上流に取水口を建設したのである。そしてその取水口から引かれた水は、神田川の本流のすぐ北側を並走し、現在の小石川後楽園である水戸藩邸を通り、水道橋付近で、今でいう水道橋、当時の呼び名『掛樋(かけひ)』によって神田川本流の上を通り、江戸の街へと供給されていた。駅名としても残る“水道橋”という名は、この掛樋に由来しているのであった。
ちなみに江戸時代の水道網は石樋や木樋で江戸街中の地下に張り巡らせられ、なんとその総延長は150キロにも及んでいたというのだから驚きである!よく時代劇などで長屋の井戸が登場するが、あの井戸も江戸の街に関していえば、地下水を汲み上げる井戸ではなく、この上水から供給された水が溜まっている“上井戸”と呼ばれるものだったのだ。
その事実を知ったうえで改めて神田川を眺めると、なにか手を合わせたくなる気分ですらある。さて。現在の神田川の本流は、水道橋からお茶の水、秋葉原、浅草橋を経て隅田川へ注ぐが、この水道橋~秋葉原間も神田上水開設と同時に掘られた流れである。それまでは今も残る日本橋川のルートで流れていたが、洪水対策で本郷台地を大規模に掘削。渓谷状の谷間を造り、そこに神田川を通したのである。今、JRの線路までもが張りつくように敷設されてる神田川のあのちょっとした渓谷は、江戸初期に、ほぼ人力で掘られた場所なのである。恐るべし、江戸初期の土木工事技術!
そんな先人たちの偉業に想いを馳せつつ散策する神田川の水面は、なにか神々しさすら感じられるのだった。