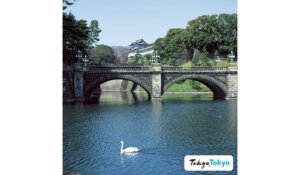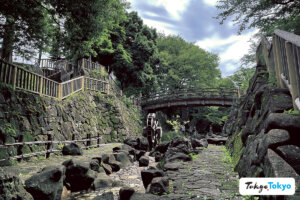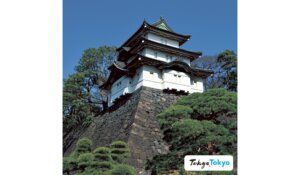代々伝承してきた古典的技法を守る江戸前寿司の本流を気軽な雰囲気で『弁天山美家古寿司』@浅草 創業慶応2(1866)年
形あるモノはどんなに大事にしても壊れたり無くなったりしてしまう。けれど技や文化は時を超えて受け継がれる。
1日1日が1年となり、10年、100年、150年……親方の手から生み出される握りは、代々受け継いできた魂のようなものが宿るのではないか。
初代は江戸前寿司の始祖とされる華屋与兵衛の流れを汲む「千住みやこ寿司」で修業。5代目の内田正さんは御年79歳だ。
「生の魚を握る現代の寿司はいわば“生寿司”ですが、うちは古典的技法の寿司。昔は冷蔵庫もないからネタをおいしくするため、煮る、〆る、漬けるなど下ごしらえした。教わった技を弟子に繋げる、その伝承がうちの味です」
大事にするのは、酢飯、仕事を施したネタ、煮切り醤油やツメ、山葵、この4つのバランスだ。
ゆえに店の酢飯に合わないと判断し、寿司として握れないウニやイクラは出さない。
浅茅 6050円(にぎり10カン・内容は仕入れで変わる)

握りは食事として満足できるようやや大きめ。マグロのヅケは柵取りして湯引きし、醤油が中まで入り過ぎないよう工夫するのも代々の知恵。
ちなみに切り身でなく柵のまま漬ける技は、この店が始めたといわれている。
実は昭和30年代に客が激減した時期もあった。流行りにおもねることなく、伝統を頑なに守っていたからだ。
「でも続けていると昔ながらの味に着目してくれる人もいてね。継続は力なり。たかが寿司屋、されど寿司屋でありたいと思っているんです」。
そう笑う親方の横には15歳からこの店で修業して34年になる6代目の姿が。
江戸前寿司の魂のバトンは、次代へ繋がれる。
5代目親方の内田正さんと6代目親方の山下大輔さん「古典的技法を守り続けることを大事にしています。」
[住所]東京都台東区浅草2-1-16
[電話]03-3844-0034
[営業時間]12時~14時半(14時LO)、17時~21時(20時LO)、日・祝12時~18時(17時LO)
[休日]月、第1・3日
[交通]地下鉄銀座線浅草駅7番出口などから徒歩3分