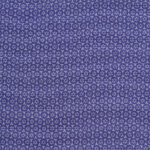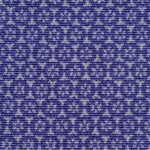江戸時代の暮らしに使われていた銘品は、今もなお職人さんの手によって作られています。江戸時代から続く伝統を受け継ぎ、そしてつなげていく──。そんな職人さんの今を知るべく、工房へ伺いました。
江戸時代、贅沢を禁じられた武士たちが、一見無地に見えるよう着物の柄を細かくした……。
これが「小紋」の始まりと言われる。いわば苦肉の策で生まれた小紋が、やがて「江戸の粋」として武士階級だけでなく、町人の間でも大人気に。江戸小紋の伝統を守る、小宮染色工場3代目小宮康正さんにお話を伺った。
伝統とは人から人へ、思いをつなげていくこと
「伝統というと、昔ながらにやっていればいいと思われがちですが、そうではありません。改良の連続によってこそつながっている。ですから、伝統とは実は『最先端』なんです」
小宮康正さんが語り出した、「伝統」への考えは意外なものだった。
江戸小紋の作成過程は、実に細かい手仕事の連続だ。
和紙で作られた渋紙に紋様を彫る「型紙」づくり、生地に型紙をのせて糊をのせていく「型付け」、その後生地全体を染める「地染め」をした後、「蒸し」、「水洗い」「乾燥 」……気が遠くなるような時間と手間をかけて、江戸小紋は生まれる。
「いまだにこんなことをしてるんだ、と思いますよね」
その工程を説明してくれる小宮さんは笑う。中でも特に繊細な、「型付け」の作業を見せてもらった。
わずかな灯が、作業場となる「板場」を浮かび上がらせるほの暗い工房。まずは、糊を塗った板に白生地を張り、型紙の上から糊をつけていく。彫幅40㎝ほどの型紙をずらしながら、一反すべて終えるまで約80回も同じ作業を繰り返す。
「『型』にも微妙なクセがあるんですね。どうしても曲がったりするので、髪の毛何分の1というところを微調整しながら進むんです」
少しのズレでもそれが重なれば、1反が終わる頃大きなゆがみになってしまう。職人の精神統一が必要だ。工房の湿度や明るさも厳密に管理されており、「本来は、作業中一切他の人はいれません」と小宮さん。黙々と繰り返される手仕事。
それは、まさしく「昔ながら」そのものに見えるが――。